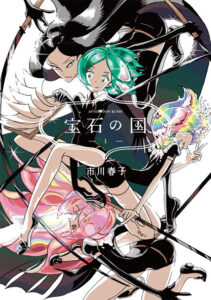第46回日本SF大賞エントリー一覧
皆様にエントリーいただいた作品とコメントを表示しています。
ご応募いただいたエントリー内容の確認が終わりましたら、このページに掲載いたします。ふるってご応募ください。
-
No.139
比良坂新 劇場アニメ『忘星のヴァリシア 第二章:群青』
第一章は地方上映のみのためYouTube視聴だったが、今作はトリウッドに足を運んだ。
約2年ぶりの続編となるが、飛躍的に品質も上がり映画として耐えうる作品になっていた。
配給の零合舎ともども「百合」をかけ合わせたSF作品として、稀有なインディーズ発の作品として、個人制作アニメとしても引き続き注目している。 -
No.138
山本ジャスティン伊等 『想像の犠牲(戯曲+上演記録映像)』 Dr. Holiday Laboratory
本作は、タルコフスキー『サクリファイス』や石原吉郎の詩を参照しつつ、ロシア‐ウクライナ戦争を背景にした戯曲である。戦争により個人がある役割を強制されることや、『サクリファイス』において女性が男性側から魔女の役割を表象を批判的に扱いながら、戯曲や演出によって、俳優が「役」としてみなされる演劇というジャンルにラディカルな問題を重ね、社会と演劇にまたがる「役」の倫理を問う。
また、「中止になった公演について、当時の出演者らによる証言を戯曲に組み込んだアーカイブ版の再現」というメタフィクションを採用することで、過去に類のない強度を持つ戯曲となっている。
ロームシアター京都×京都芸術センター U35創造支援プログラム“KIPPU”採択作品であり、ロームシアター京都ノースホールおよび吉祥寺シアターで上演された本作は、戯曲上演ともに上田洋子氏や保坂和志氏等、他ジャンルの作家や批評家にも高く評価された。 -
No.137
河野咲子(脚本) オペラ『船はついに安らぎぬ』
オペラのリブレットとは、音楽に従属する台本ではなく、言葉そのものから音楽が立ち上がる存在であるべき――本作はその詩学を鮮烈に思い起こさせる、稀有な到達点である。SF的発想を果敢に導入しつつ、作曲家との綿密な協働を経て、「幻想怪奇オペラ」という新領域を切り拓いた意義は大きく、日本のオペラ史に新たな地平を拓く作品と言える。本作の初演を担った演出家として、心より推薦する次第である。
-
No.136
サイトウマド 漫画『怪獣を解剖する』 KADOKAWA
死んだ怪獣を解体処理する現場で、オッサンたちに混じって奮闘を続ける若き女性科学者が主人公。お仕事マンガという体裁をとりつつも、調査対象であり未知の象徴としての怪獣、災害の象徴としての怪獣の姿をあらわにする。身に迫るリアルなエピソードを積み重ねた傑作で、今時あれこれ数多あるどの怪獣マンガよりもたぶんもっとも先進性のある怪獣SFであると思う。
-
No.135
著:奈須きのこ(原作:TYPE-MOON、開発:LASENGLE、運営:アニプレックス) ゲーム『Fate/Grand Order Cosmos in the Lostbelt』より「奏章Ⅲ 新霊長後継戦アーキタイプ・インセプション」
本作は新しい霊長を決める戦いのなかで「人間とは何か」という根源的な問いを描いた傑作です。
人類が自分たちで作り上げた技術であるAIを、自分たち以上の存在として認めることができなかったが故の滅び。
そんななかで著者がこれまでの作品のなかでも描き続けてきた「後に続くものたちに繋いでいくために今を生きている」をはじめとする人間讃歌たち。本作がリアルタイムで読者を巻き込んでいくスマートフォン向けRPGという媒体で描かれた点も推薦する理由の一つです。
URL1:https://news.fate-go.jp/2024/ordeal_call_3/
URL2:https://www.fate-go.jp/ -
No.134
宮澤伊織 『ウは宇宙ヤバイのウ!2 天の光はすべて詐欺』 早川書房
シリーズ1作目の〔新版〕は版元変更を機に百合SFへと改稿された作品だったが、2作目の本作品は最初から百合SFとして構築されている。後期ダーウィンの重要概念である「性淘汰による遺伝子レベルの進化」は無意識的なヒトの行動方針を決定するが、ヒトは感情で行動を選択するため、進化的行動様式と感情反応のズレが葛藤を生む。本来、異性に対して発揮されるべき恋愛感情を、同性や異種生命体を対象に拡大することで、SF物語として成立させている。クライマックス直前で繰り出されるDIY兵器は、これひとつでワン・アイデア・ストーリーを成立させうる秀逸なガジェットだ。デイヴィッド・ブリンの知性化シリーズを現代的にアップデートした上で、海外SFのエッセンスを凝集し、ワイドスクリーンバロックへと構成した著者の力量は特筆に値する。その先へ、ブラックホールと量子力学を扱う本格SFへと転回を果たした本書は、奇跡的な大傑作である。
-
No.133
村田沙耶香 『世界99』 集英社
〆切十分前時点で掲載済みの前々日投稿分まででまだこの作品が出ていないのはありえないのでエントリーします。主人公は子どものころからその時々に接している相手・集団に受け入れてもらえる人格をいくつも設定し、それを切り替えて生きてきた。その場その場ではその人格になりきりつつ、自分がつねにそういう状態だという認識があり、すべての人格の背後に「真の自分」とかが存在するわけではない。彼女はある年齢まではほかの人もみんなそうしているものだと思っていたが……じっさいはわれわれも多かれ少なかれそういう生き方をしていて、文学作品が個々に掘り下げてきたような一貫した「個人」など存在しないのでは。それを描き抜いたこの作品のあとでは、SF作品に対する低評価の定番フレーズ「人間が描けていない」はむなしい。作品の凝った近未来設定や、それを含めた高評価は版元の特設ページなどでいくらでも語られているのでそちらをご覧ください。
-
No.132
龍村景一 『ツッパリ探偵怪人メルヘン心中』 トーチ
題材もモチーフも絵柄も手法さえも、一見バラバラに思えるような短篇マンガの読切が並んでいる、ように見える。しかし、物語の内側と外側を繋ぎ、解き、新しい景色をもたらそうとする意志は、驚くほど一貫している。SFのジャンルでこれまで試みられた「現実とその解体/再構築」といったテーマに大きな一石を投じており、かつ、各篇の質も極めて高い。(とりわけ、「生成AI」のモチーフをメタファーとしてのみならず、マンガ技法としても取り込んだ「心中遊泳」は驚くべき傑作といえるだろう。)現実と非現実のカオスを、確固たる意志で突き進んだ末に生まれた見事な作品群は、優れたスペキュラティブ・フィクション(SF)の一つの達成であると判断し、推薦いたします。
-
No.131
小野俊太郎 『P・K・ディックの迷宮世界: 世界を修理した作家』 小鳥遊書房
「今となっては信じられないだろうが、P・K・ディックを、(中略)大量生産の作家にすぎない、と低い評価を与える傾向があった」から始まる本書は、ディックの初期中短編5作品を中心に扱った評論だ。すでに評価されているディックを再評価をしているわけではなく、“評価されていなかった時代”にあえて戻って、「主流文学作家」として読み直すような試みが汲み取れる。タイトルは「迷宮世界」とされているが目的は、彼の作品からえられる「温もり」の正体の解明である。ディック中毒者にとってはその中毒の理由がわかるかもしれない。新しいSF評論としてぜひ推薦したい。
-
No.130
赤野工作 『遊戯と臨界: 赤野工作ゲームSF傑作選 』 東京創元社
令和の現代におけるインターネット文化と、ゲームという題材を軸に繰り広げられる人間ドラマを見事に切り出した傑作短編集である。
各作品を通して書かれるは、ゲームをプレイした事のある者なら全員心当たりがあるであろうゲーマーの本能。ゲーセン・ソシャゲ・実況・オンラインと、ゲームという文化が大衆にも広く浸透したこの現代、本作ではSFを通して、そして、あらゆる時代のあらゆる場所に存在するゲーマーという生き物を通して、ゲームの可能性を示している。この作品は、ゲームの新時代を肯定し、ゲームという文化が持ちうる無限の可能性を示す一冊なのである。SFを通じてそれを指し示した功績はSF大賞にもふさわしいと考え、本作品をここに推薦する。 -
No.129
飛浩隆 『鹽津城』 河出書房新社
自薦。著者の作品集はシリーズ物を除けばこれが三冊目に当たる。収録作の主な初出媒体が一般文芸誌だったことも影響してか、現代もしくは近過去の日本の風土を前面に出し、権力による管理や気候変動など著者がこれまで扱ってこなかった主題を扱うなど、過去のどの作品集とも異なるものとなった。その成否を選考の俎上に載せていただきたく日本SF大賞にエントリーします。
-
No.128
カリベユウキ 『マイ・ゴーストリー・フレンド』 早川書房
SFの楽しさのひとつは、「なにが起こるかわからない」闇鍋的なワクワクさであろう。最終的にどこへ行き着くのかわからない、地に足がつかないようなフワフワ感を与えてくれる作品はあまり多くない。本作は、団地ホラーから始まり、ギリシャ神話を経由して、最終的にSF的超理論に行き着くという浮遊感と酩酊感を与えてくれる作品であった。登場人物たちの真剣なようでどこかとぼけた会話劇も相まって楽しい。「ジャンル横断の旅」をさせてくれる作品であり、SFの歴史に新たな側面を付け加えた作品である。
-
No.127
村田沙耶香 『世界99』 集英社
ノエル・キャロル『ホラーの哲学』では、ホラーの対象は「危険なもの」であるのと同時に、カテゴリを侵犯する「不浄なもの」であるとしている。だが、もし、その「不浄さ」が世界を成り立たせる根本的な出発点である「自分」から放たれていたらどうするのか?「自分」の本質だと思っていたものが、外部のフレームによって決まっていたら?本作は、「われわれ」の前提のはずの「自分」という概念を執拗に溶解させていく。内宇宙を探求する実存ホラーSFとして、これまでになかった作品だ。
-
No.126
藤原慶(監修・著)大澤博隆、長谷川愛(監修)茜灯里、柞刈湯葉、瀬名秀明、麦原遼、八島游舷(著) 『鏡の国の生き物をつくる SFで踏み出す鏡像生命学の世界』 日刊工業新聞社
鏡像生命学という科学でも概念が定まりきっていない分野に対し、専門書すら存在しない中、SFアンソロジーと科学解説が混じった入門書が世界にさきがけて執筆された異色作。鏡の国のアリスや戦闘妖精・雪風などでも出てきたネタだが、本当に作られる可能性と現在の科学技術議論に基づく詳細化から、リアリティをともなう鏡像生命の世界が広がる。増殖可能な鏡像生命は制御不能になり世界に危険にもたらすという科学者の恐れと、そうでもない未来像を描くSFが、科学的解説とともに交差する中で描かれる。世界で科学者含めて誰もまだわかっていない分野に踏み出す本として、SF史に残るものといえる。
-
No.125
監督:松居大悟 映画『リライト』
この国のあらゆるタイムリープSF青春映画は、『時をかける少女』という1983年の広島県尾道市で起こったマジックのきらめきの下に存在する。そのマジックを徹底して分解して世界を穿つ武器として組み立て直し、「SF史上最悪のパラドックス」と銘打たれた法条遥の傑作小説『リライト』が発表されてから十数年……その小説を「サマータイムマシン・ブルース」「リバー、流れないでよ」等の時間SF映画の名手である脚本家・上田誠がさらに徹底して分解し、原作のバッドエンドを潜り抜けてふたたび尾道に青春のきらめくマジックを出現してみせた、存在自体が奇跡のような時間SF青春映画の臨界点にして大傑作。練られた脚本だけでなく、当人からしたらホラーそのものだけれど傍から見たらどうしてもコメディになってしまう原作のシーンを本当にコメディで描いてしまう監督の力量にも舌を巻く。ビターだけど透き通った感動が観る者の胸に満ちる名作。
-
No.124
中西鼎原作、風呂川 ツカサ漫画 漫画『時間の神様』 集英社
もしも時間を止められる時計があってそれを付けたら。良いことだって出来放題だけれど悪いことだって出来てしまう不思議な時計をふとしたきっかけで手にした少女が、ひとりの少年と出会って楽しく時計を使っていた先である事件を起こしてしまう。時計の力を使って何が出来るのかを描くSF設定のサスペンスがあり、時計に隠されていた秘密に迫るスリリングな展開もあって全15話と短い中に濃密な物語を描き挙げた。8月28日連載終了につきエントリー。
-
No.123
トウキョウ下町SF作家の会 『トウキョウ下町SFアンソロジー この中に僕たちは生きている』 Kaguya Books
東京の下町にゆかりのある七名の作家が下町を舞台に様々な物語を織り成したSFアンソロジー。江戸っ子気質なハクビシンの軽快な語り口が楽しめる大竹竜平「東京ハクビシン」を皮切りに、江戸の粋とIoTが融合した大木芙沙子「朝顔にとまる鷹」や、隅田川の架空の生態系から自由の本質を問う関元聡「スミダカワイルカ」、地域のアイデンティティを技術的に追求する過程で、民族と文化の根本的な問題へと到る斧田小夜「糸を手繰ると」など、SFの想像力を用いて下町という空間を立体的に浮かび上がらせます。また、東京ニトロ「総合的な学習の時間(1997+α)」と笛宮ヱリ子「工場長屋A号棟」は、戦争に加担してしまう可能性とそれに抗う力を描いた作品で、今こそ広く読まれてほしいです。TikTokをタイムリープのギミックに用いた桜庭一樹「お父さんが再起動する」も、柔らかな語り口ながら根底に確かな心と思想を備えた見事な作品です。
-
No.122
飛浩隆 『鹽津城』 河出書房新社
SFとしてもエンタメ小説としても純文学としても、世界最高の一冊である。
この一冊にふさわしい推薦文など書けようもないとさえ思う豊かな小説世界。高尚で、俗っぽくて、大人で、子供の目と心を描いていて、現世や人間への怒りがあり、やがて訪れる未来への透徹した視点があり過去へのノスタルジーがある。1ページごとに恍惚感さえ感じるほどの文章表現と巧緻なプロット。永遠に畏敬され愛される作家の新たな代表作。 -
No.121
伊島糸雨 『殕花遺説』
伊藤糸雨さんが構築する精緻にして清澄な世界の魅力が散りばめられた短編集。独特の造語が見たことのない色や音に満ちた時間に連れて行ってくれる。唯一無二の世界を堪能したあとには喪失を胸に抱きつつ祈りを解き放ちたくなる。
-
No.120
井上信行 『La Luciole』
ドルフィーと呼ばれるアンドロイドたちの生涯と争いを何世紀にもわたって描いた作品。
独自の世界観や彼らをとりまく宇宙のシステムなど架空の要素や、かなり難解な箇所もいくつかあるのですが、根っこは現代日本で、虐げられる女性や社会的弱者が描かれています。作者自身が作り出した壮大なデータベースをひとつひとつ読みこんでいく感じが面白いです。
https://amzn.asia/d/3FTalI3 -
No.119
中西鼎 / 風呂川ツカサ 漫画『時間の神様』 集英社
本作は15話の短期連載ながらも、競争率の激しい「ジャンプ+」というウェブ漫画媒体の木曜日において、ほぼ毎週PV数1位を保っていたSF作品。近年ウェブ漫画は先鋭化し、紙漫画とは異なる、コマを大きく、セリフを端的に、場面展開を派手にした演出重視の作品が多く作られている。藤本タツキ作品や『タコピーの原罪』から始まった流れであろう。今後この作り方が紙漫画を含めたデファクト・スタンダードになっていくのか、一過的で局地的な流行に終わるのかはわからないが、しかし本作『時間の神様』が「現代のウェブ漫画」らしい演出重視の文法を用いて、「ジャンプ+」というウェブ漫画の象徴的な媒体で成功したことは、SF作品の歴史の中でも特筆すべきことだと思う。
-
No.118
十三不搭 『ラブ・アセンション』 早川書房
「軌道エレベーターで行われる恋愛リアリティショーに、エイリアンに寄生された人間が混じった。そしてエイリアンは、求愛の特殊能力を与えるようだ」という、コミカル設定のエンタメでありながら、高い文学性も備えた作品。群像劇として各キャラクターの生い立ちや性格が濃密に描かれており、「愛とは」「恋愛とは」の問いに、多角的かつ真実味のある描写が実現されている。
近年、若年層に訴求力のあるライトタッチのSF作家の活躍も目覚ましいものの、ジャンル小説としてのSFファンダムは高齢化が進んでいると思う。他方、純文学の畑では、SF要素を取り入れた作品の広がりも見られる。これは科学の想像力に現実が追いついたことで、科学が内包する文学面に社会が関心を寄せているからではないだろうか。このような潮流で、SFエンタメでありながら、大人向けであり、かつ純文学的な重みも持つ本作は、次の時代のSF小説の一つの可能性だと感じた。
-
No.117
三秋縋 『さくらのまち』 実業之日本社
学生時代に想いを寄せていた女の子が自殺したとの報せを受けた主人公は、長らく帰っていなかった故郷へと舞い戻り、彼女の死の原因を独自に調査しはじめる。彼が掘り当てたのは、思いもよらぬ痛ましい真相で――
筋立ては完全にミステリですが、本書の特徴として、『ハーモニー』のを思わせる健康管理デバイスの存在が挙げられます。
善意による締め付け、安定と自由のトレードオフといった古典的ディストピアSFの流れを汲みながらも、「フェイクに溢れた世界で、如何にして他者を信頼するか」という、現代人に突き刺さるテーマを描ききった傑作です。
公式のあらすじではSF設定について触れられていないため、本作を見逃しているSFファンも多いのではないでしょうか。一人でも多くのSFファンが、この傑作に出会えるよう、推薦させていただきます。 -
No.116
伊藤典夫 『伊藤典夫評論集成』 国書刊行会
戦後日本SFがどのようなものかを知るにはこの本を読むに限る。英米のSFを紹介するにあたって、著者は、SFとは何か、それがどのように形成され、どう変化してきたのかを、一生かかって考えつづけてきた。その思索の全てが一冊にまとまったのだ。これほど貴重なものはない。
-
No.115
犬怪寅日子 『羊式型人間模擬機』 早川書房
とても奇っ怪で、おそろしくチャーミングな物語。少女アンドロイドが、「羊の儀式」に向けて、仕える一家の人々を紹介してゆくが、それぞれが風変わりで魅力的。どこからこんな世界が湧いて出るのか不思議でしょうがない。
-
No.114
飛浩隆 『鹽津城』 河出書房新社
この作品集を読むと、SFが小説の可能性をどこまでも広げる可能性をもっていることがわかる。題材といい、手法といい、決まりきった枠を超えて、新しい世界を切りひらいてゆく、その成果がここにある。洗練され、挑戦的で、そして豊饒。
-
No.113
十三不搭 『ラブ・アセンション』 早川書房
恋愛リアリティを題材にした、とてもエンタメでありながら、縮図のような「軌道エレベーター」の中で、恋の成熟に多様な期待を寄せる参加者たち。そこで愛の完成が、全てを打ち破って、行方不明になり「我々の知らぬところ」へ行くのは既知の価値観を超越して、全ての再定義を示唆するかのようなSFでした。このような「人の飛躍」をイメージさせる本作を、希望の灯火として、日本SF大賞に推薦します。
-
No.112
伊藤典夫 『伊藤典夫評論集成』 国書刊行会
戦後日本SF史は翻訳から始まった――そう豪語しても構わないとすら思うが、翻訳家の評論はしばしばSF業界における「二級市民」とみなされ、充分な評価の対象となってこなかった。著者は本賞の1回から7回まで選考委員をつとめてさえいるのに。本書において、英米SFの受容と批評は車の両輪のごとくに切っても切り離せないものであり、高名な「SFスキャナー」をはじめ、膨大な時評の数々は、未訳SFの海に飛び込む際のまたとない羅針盤、あるいは友となるべきものである。とりわけ、未訳SFの翻訳やアンソロジーを編む機会が多い我が身にとっても啓発的である。今日においては更新されるべき情報や知見もまま見られ、そのまま鵜呑みにはできない部分もあるのだが、検証を厭わせないだけの熱気が備わっている。高価な1冊ではあるが、素晴らしい内容で、繰り返し繙かれるべきだろう。
-
No.111
森泉岳土 漫画『ソラリス』 早川書房
スタニフワフ・レムが小説『ソラリス』を発表してから60年以上の歳月が流れ、その間、映画やテレビドラマ、演劇、オペラ、ラジオドラマなど、さまざまな媒体の原作として表現されてきた。しかし当然のことにいずれもが、その表現者の解釈と価値観によって上書きされたものである。しかしマンガ版『ソラリス』の森泉氏はそうではなく、まず原作者の意図を読み取ることに専念し、それを絵として具現化していくことに創造性を感じたという。氏の関心と表現欲の源泉は、レムの意図の深淵にこそあったのだろう。ゆえに氏のマンガ版『ソラリス』は、数多ある今までの映像や舞台として出現した『ソラリス』表現とはまったく異なる、『ソラリス』の具体的表現として、私たちの目の前に登場したことになる。その絵には難解といっていいレムのソラリス自体のありようが、まさに映像的に展開している。私たちは60年掛かって、初めて『ソラリス』を見たのである。
-
No.110
ケン・St.アンドレ 著 岡和田晃 訳 『ズィムララのモンスターラリー・ワールド編』 FT書房
現役最長老のRPGデザイナー、伝説の霧に包まれしトロールゴッドファーザーことケン・St.アンドレによる、新しい架空世界の設定資料集。“なんでもあり”を謳う異世界は数あれど、他の誰が創ってもこうはならないだろう。古き良きSF風の月の下、アメコミの通俗性とアルカイックな神秘性が無理なく同居するキッチュでオーセンティックな宇宙は、RPGの面白さを知り尽くした知的趣味人たる彼の面目躍如だ。かつて彼が創造した世界におけるモンスターは、「人間への反逆」の象徴だった。その任から解き放たれたクリーチャーたちが跋扈するこの新世界は、人間すら元の姿ではいられないトランスヒューマン・スペースだ。ここで異種族を演じる君を待ち受けるのは、悪魔か、神々か、はてまたは生体サンプルを求める宇宙人か? これまで蓄えた小賢しい知恵は投げ捨てて、RPGが本質的に持つ、プリミティヴな楽しみに酔いしれてほしい。
-
No.109
脚本・河野咲子(作曲・永井みなみ) オペラ『船はついに安らぎぬ』
SFの源流は人ならぬ存在への思い、未生と死、異界への恐れ。西洋古典に遡れば叙事詩、そして戯曲。そこから歌う物語、音楽への憧れとしてオペラが生まれた。E.A.ポオの「赤死病の仮面」を下敷きに、陸地がほとんど水没した地球を走る船の物語。リブレットの言葉の美しさに、音楽と歌が翼を与える。新しく日本語によって作られるオペラという音楽劇の持っているsense of wonderをSF&幻想文学愛好者の皆様に知って欲しい。
初演時作品紹介ページ
https://opera94.main.jp/web/06funeginu/
脚本・フルスコア販売フォームhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI8GG0gUECXCD1Lo4zjrolPJZSlxvRga1A7KUjt6zL_aFjzA/viewform -
No.108
小野俊太郎 『P・K・ディックの迷宮世界: 世界を修理した作家』 小鳥遊書房
ディックのみを論じた一冊。ディックがなぜ読むものの心を引きつけ続けるのかの理由を探ったSF評論。『宇宙の眼』『高い城の男』『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』『流れよわが涙、と警官は言った』『ヴェリス』を丹念に分析されている。すでにディック作品に溺れている人も、本書を通じて新しい読み方に気づくと思います。
-
No.107
藤井亮 映画『大長編 タローマン 万博大爆発』
2022年のTVシリーズでは、解説役のサカナクションの山口一郎さんが、存在しないタローマンの記憶を語り、それにならって存在しないタローマンの記憶を語る視聴者が続出した。
その影響は、つい先日、山口さんがNHK総合の「クローズアップ現代」でイギリスの世界的な人気ロックバンドoasisについて語ったところ、伝説のバンドoasisなんて本当は存在しないのでは、と思わせ不安にさせるくらい絶大である。NHKには責任を取ってもらいたい、具体的には地上波でもっとoasis関連の番組を流すとか。
という私怨はともかく、タローマンの出現以降、タローマンの存在しない世界は考えられないのだから、まさにSF大賞にふさわしいべらぼうな作品である。そう岡本太郎も言っていた(ない)。
2022年時にTVシリーズを推薦しなかったのを、少しく悔いていたので、大長編によってエントリーできてうれしい。 -
No.106
双葉すずき 『グッバイ、ペンローズ』 リイド社
「ペンローズの階段」をモチーフとして徹底的に使い倒した傑作。二人の友情についての語りと、宇宙の始まりと終わりの仕組みが、「流しそうめん」によって結び付けられるアクロバットな発想が素晴らしい。日常的な光景から作中世界の構造の開陳に向かう際の飛躍が瑞々しい。時空間のスケールの大きさと心情描写の繊細さを両立させていく面白さは、SFマンガでしか成し得ない大胆さでもって、見事に結実している。
https://to-ti.in/product/futabasuzuki -
No.105
堀井拓馬 「塗る喰ら」(水那小会『発禍点』所収)
お文学フリマで刊行された、プロ作家の方々による同人誌に収録された短篇です。商業出版でのSF発表の場が狭く狭くなっている現在、お文学フリマからSF大賞が生まれたっていいんじゃねーの、と思いました。日本のSFはもともと同人誌から始まったもんなんだからさー! 同誌には、ミステリー寄り・ホラー寄りのSF境界作品も多いのですが、最も純粋にSF作品であると解釈できる『塗る喰ら』を推します。架空の科学用語、造語が頻出するのは近未来SFの宿命ですが、本作では最重要のキーワードが「アナフィラキシー」という実在語彙であること。そこに現実変容のマジック、今と地続きの異界、グルメ文学の新地平を感じました。ナニ言ってんだオレ。(というか今年からSFマガジンの購読を止めたので、読んだ新作SFがコレだけだったのです)
-
No.104
早海獺 「袋のなかはビッグバン」
いつもテーマ設定が魅力的なマガジンKAGUYA Planetのプラネタリウム特集で読んだのが本作です。この世界を一瞬で消してしまうものが、ファン垂涎のグッズとなり、軽はずみな誰かの手に渡ってしまったら…という状況が、決して未来の話ではないことを自分がすでに知っていると気づく作品。ショップの常連さんが披露する、地球の地軸の傾きを詠んだ俳句で心を完全につかまれました。
技術の革新もファングッズの開発も、きっとどんどん加速していくけれど、人はたいして進歩しないという哀笑と、でもユーモアや親切さ、そしてうたを詠む心は続いていくのだという強い気持ちが、長くはない文章にこれでもかと注ぎ込まれたディティールに貫かれているようで、心に残った一作です。 -
No.103
岡和田晃 『世界の起源の泉』 SF ユースティティア
海外にはライスリング賞というSF詩の賞がありますが、日本に相当するものはありません。変ですよね。SF大賞はそこに風穴をあけるべきではないでしょうか。本書は2019年から2024年までに書かれたSF評論でおなじみ岡和田晃さんの書いた現代詩をまとめた詩集なのですが、古典的な幻想文学からおなじみの思弁小説までをふまえ、高精度なヴィジョン、硬質な文体、物語性あふれる展開、社会批判――とても複雑で精妙な書法がとられており、北海道新聞文学賞の候補になったというのもうなずけます。騙されたと思ってお読みなさいな。
-
No.102
森下一仁 『エルギスキへの旅』 プターク書房
小説は作家が書くものだが、読者の夢でもある。本書は30年前にSFマガジンに連載された作品だが、今年初めて単行本化された。ファンが一人出版社を立ち上げクラファンによって出版にこぎつけたのである。これまでは決して実現しなかったSF読者たちとSF作家の夢の結実は、本書以前には見ることのできなかったものだ。
端正な文章で描かれる異文化と少年の成長。普遍性の高い、押しつけがましさはないのに記憶の中に一生残るだろう感動。
埋もれた傑作は、今後も様々な方法で掘り起こされ再発見されることだろう。
本書はその嚆矢でもある。
作品とともに出版の経緯も含めて日本SF大賞に推薦する。 -
No.101
天沢時生 『すべての原付の光』 早川書房
本書は日本SFの新生面を拓く短編集である。
天沢時生はゲンロンSF新人賞と創元SF短編賞の受賞者(受賞時はトキオ・アマサワ表記)だが、まるでSF小説のジャンル内で小説を書こうとしていないように思える。「SF」の自由さを利用してほとばしる情熱を読者にぶつけているように読めるのだ。「SF」で遊び、苦しみ、笑い、走り、転び、呻吟しどこまでも飛翔してくれる。作品の多くは“地方ヤンキー“という、従来のSFファンとは対極にある人物を中心に据えている。その人物や世界が、魔術的なセンスと文章のうまさによってカッコわるさがかっこよさに、シャレにならないダークサイドな行為が笑いに、閉ざされた辺境が世界を開く力に変換されている。
「SF」は、内側からジャンル概念を食い破る作家の登場によって世界を広げてきた。
天沢時生はまさにその一人である。本書は新しい世界観と人間観をみせてくれた。 -
No.100
荒巻義雄 『聖シスコ電説』 小鳥遊書房
「マジックキューブ」というおもちゃをご存じだろうか。絵柄の描かれた立方体に切り込みが入っており、その切り込みを開くと別の絵柄が現れる。また別の切り込みをくるりと開くと、別の絵柄に変わる。次々に展開する絵柄を見ていると、まるで無限に思える構造が立方体に内包されているような気になるのだが、本書はまさに『高い城の男』というディックの小説という立方体の構造を解きつつも、その一部の絵柄にならんとするような実験小説ではないかと感じた。「歴史」の層を開き、また宕見(タゴミ)を主人公に据えることで、ディック論を小説内で展開している。著者の言う「借景」は、まさにSFならではの楽しみ方を読者に与えてくれるのではないだろうか。
-
No.99
冲方丁 『ムーンライズ』 TOブックス
Netflix配信作品『ムーンライズ』の原案小説。
AI「サピエンティア」による管理のもと、豊かな生活を享受する地球人と、月で過酷な労働生活を強いられるムーン・ピープル。その、現代社会にも通底する格差社会が、月側の一撃『グレート・フォール』により一転。反逆の戦いが幕を開ける――。
月での暮らしや闘いが、現実的な物理条件を踏まえた上で描かれているのでリアル感がある。宇宙SFとして、アクション・エンタメとして、そして人間ドラマとして、全方向で楽しめる小説。 -
No.98
スタジオカラー、サンライズ TVアニメ『機動戦士ガンダムGQuuuuuuX』 スタジオカラー、サンライズ
いまや誰もが知る巨大IP『ガンダム』にはいくつかの変曲点があった。続編(Zガンダム)制作による宇宙世紀史の延伸、Gガンダムによる非宇宙世紀世界への展開、SDガンダムによる非リアル系世界の創造と新たなユーザ層へのリーチ。それら局面は創造的破壊にほかならず、新たは需要者層を創出し、そうした革新の連続が「ガンダム」という伝統を作り上げてきた。
2025年に放映された『機動戦士ガンダムGQuuuuuuX』もまた、そうした変曲点のひとつである。宇宙世紀史にメタバース的方向性を取り入れ、ガンダムという作品世界をこれまでにはなかった次元方向へと拡張、さらにスタジオカラーという新しい風を取り込むことで、ファン層の新陳代謝を促した。「ガンダム」ほどのIPがなお新たな地平に挑戦し、進化を続けようとするマイルストンのひとつとして、本年のSF大賞にふさわしく思われる。 -
No.97
坂月さかな プラネタリウム・ゴースト・トラベルシリーズ パイ インターナショナル
『坂月さかな作品集プラネタリウム・ゴースト・トラベル』『星旅少年』を含む本シリーズは、〈ある宇宙〉と、眠りに就こうとする星々、そして星旅人の物語である。美しくも不穏で壮大なセカイの成り立ちに触れながら、「旅」と、旅が織りなす人々の息遣いも本作の醍醐味だ。多様な人々、文化、生活、香り、物語に満ち、人やモノとの出会いは珍奇で奇想天外。異国の小道を旅するような驚きを読者は追体験できる。
過去にはコンビニプリントでも作品世界が展開されるなど、遊び心に満ちた著者の〈ある宇宙〉に応えるように、様々な二次創作やファンアートが創られ、コラボカフェも展開するなど、本シリーズはSFの受容層を大きく広げる。また、六か国語に翻訳され、日本人初となるボローニャ・ラガッティ賞を受賞するなど、海外での評価も高い。第54回日本漫画協会賞・漫画部門で大賞受賞。
-
No.96
新馬場新 『歌はそこに遺された』 徳間書店
本作は、生成AIが音楽産業を覆う近未来日本を舞台に、遺作となった歌の作者と、その謎を捜査と法廷で突き詰める近未来SFである。証拠の積み上げが合理的かつ、反転の連続が鮮烈だ。読後、これは明日の現実だと確信させられた。ミステリー仕立てで科学の恐怖と希望を描いた本作と、近未来SFに意欲的に取り組み続ける作者を本賞に推薦したい。
-
No.95
赤野工作 『遊戯と臨界: 赤野工作ゲームSF傑作選 』 東京創元社
近未来でも、宇宙空間でも、月でもディストピア社会でももちろん令和の日本でも!たかがゲームにグチグチウダウダワヤワヤグダグダ抜かしたいのは、科学がどれだけどんな方向に進んだとしても変わらないのかもしれない。ゲームに人生を捧げるほど楽しみたい愚かで狂ったゲーマーたちに時として笑わせられ、鏡を見ているような気持ちになって時として苦しめられ……そして、全編通して誰もがとんでもなく愛おしい、未来にも宇宙にもオススメしたい傑作短編集。
-
No.94
麻根重次 『千年のフーダニット』 講談社
様々な思惑を抱えた7人の男女が1000年後にコールドスリープから目覚めると、仲間のひとりが明らかに他殺された状態でミイラ化していた。さらに施設内を調べると、今度は顔の損なわれた「いるはずのない8人目」の死体が。絶対不可侵の施設内で爆睡かましてるあいだにいったい何が起こったのか? 千年越しのフーダニットミステリが幕を開ける――と、この設定だけでも生唾ごくりものだが、本作はただSF設定で「そして誰もいなくなった」をやるにとどまらず、さらにSF的な飛躍を見せる大仕掛けを施しているところが魅力である。本書はミステリ好きに広く薦め概ね好評を得られたわけだが、ミステリとして売られたせいかSF好きのあいだでは認知度がまだ高くない。しかし本作は前述の通りSFとしての強度も強く、何より小説として「面白い」。SFでありミステリでありロードノベルであり「生きる」ことを問う物語である本作を日本SF大賞に強く推す。
-
No.93
荒巻義雄 『聖シスコ電説』 小鳥遊書房
荒巻義雄「聖シスコ電設」(小鳥遊書房)は、世界が情報に席巻される時代に、人間の拠り所はいったい何かを深く問いかける。F.K.ディックへのオマージュとして書かれたというものの、長年に渡る思索と多くの創作活動から到達した本作は、一 SF作品を超えて、現代文明への深い省察となっている。理性、信仰、幻想、そして電脳、さまざまに交錯する世界にあって、哲学的命題を軸に果てしない世界を考察し続ける姿は驚異的である。今後のSFのあり方を問う一冊となっていることを読み解く必要があろう。
-
No.92
荒巻義雄 『聖シスコ電説』 小鳥遊書房
ディックの『高い城の男』という歴史改変SFをさらに改変させて地政学的にもパラレル、立体構造で浮かび上がらせる荒巻イズム全開の傑作である。SFがどのように再構築(リコンストラクション)されるのか、本書を読んでワクワクするSFファンは多いはず。
-
No.91
伊島糸雨 『殕花遺説』
自薦です。昨年11月に刊行した本作品集には、anon press掲載作のほか、B F C3(ブンゲイファイトクラブ3)本戦出場作、株式会社LIXIL主催のSFアワード最優秀賞受賞作など、2023年のデビュー前後に執筆した選りすぐりの10篇を収録しています。SF/ファンタジー/現代詩/神話等々、「百合SF」の文脈における探究として書き続けてきたエッセンスを盛り込みつつ、万物の未来において普遍的な「喪失」とそこから生まれるものに向き合った作品集です。
中でも、表題作である「殕花遺説」は、漢字を用いた造語と硬質さと柔らかさを併せ持つ文体で終わりゆくひとつの世界を描いた力作であり、これまでに培ってきたものがよく現れているものと考えます。
以上から、自身が名刺にする作品集のひとつとして、また、新人作家である自身への期待も込めて、日本SF大賞に推薦いたします。
-
No.90
冲方丁 『ムーンライズ』 TOブックス
地球と月の間で独立戦争が勃発しました。この血みどろの戦いを終わらせるために必要なこととは何でしょうか? そう、選挙ですね。民主的な方法で議員を選び、月議会を発足。その上で地球政府と対等に交渉しなければ真の独立は果たせません。SF超技術でドンパチし合う時代は終わりました。これから選挙の時代です(まあそれはそれとしてドンパチはしますが)。ところで『マルドゥック・アノニマス』でも新刊で選挙やってますね。作者のマイブームなんでしょうか。
-
No.89
小野俊太郎 『P・K・ディックの迷宮世界: 世界を修理した作家』 小鳥遊書房
ディック本人の評伝ではないのでそれを期待すると裏切られる。だが、ディックのイメージは、『ブレードランナー』という映画の原作者という面が強かったが、小説の側から見ると雰囲気がまた違う。映画と小説との比較がある。もう一つは『高い城の男』を日本にこだわって読む点だろう。
-
No.88
藤井亮 映画『大長編 タローマン 万博大爆発』
TVシリーズとして始まったタローマンは劇場版映画として完成形を見ました。存在しない過去と未来と作品という虚構を観客全員で鑑賞し共有し愛でるという体験を含めて、でたらめでべらぼうなSFでありアートだと確信します。なんだこれは!
-
No.87
瘤久保慎司 『錆喰いビスコ』 KADOKAWA
巨大な蟹の背中に乗り、鉄鋼をも貫く弓矢を放てばキノコが「咲く」。強弓で強敵を痛快に倒していく少年二人の冒険譚だ。本作をSFとして捉えるには、キノコを重要なアイテムとして扱っている点を挙げれば十分だろう。ポストアポカリプスな世界観の作中に登場する多彩な性質を持ったキノコは、武器となり、薬となり、物語に四次元のふくらみを与える鍵となっていく。過酷な世界を生き抜いた進化生物も独自のビジュアルや特徴を持ち、想像をかきたてられる。そして優れたブロマンス小説でもある。ビスコとミロの関係性だけでも十分に魅力的な物語だ。作者の瘤久保氏は巻末あとがきで作品の意図を端的に語るのだが、一巻の巻末には「愛」と記載している。全一〇巻を読了した今、一筋の「愛」が全編を貫いていたことがわかる。まだまだ多くの人の心を射止める可能性を秘めた物語であると信じている。極限状態で生まれる名台詞の数々に、魂を揺さぶられてほしい。
-
No.86
原作:TYPE-MOON、開発:LASENGLE、運営:アニプレックス ゲーム『Fate/Grand Order Cosmos in the Lostbelt』より「奏章Ⅲ 新霊長後継戦アーキタイプ・インセプション」
大人気ソシャゲ『FGO』の2024年夏イベントは何から何まで異例尽くしだった。2023年末に参加条件が発表されたこともその参加条件にかなりの進行度が求められたこともファンを驚かせ、次第に情報が解禁されるなかでそれがメインシナリオへ直接繋がると明かされると驚きは期待による胸の高鳴りへと変わった
そんな鳴り物入りで公開された夏イベとそれに連なるメインシナリオ(即ち、今回のエントリー作品)、その構成要素をすべて挙げると文字数制限を優に超えそうなのだが、そのシナリオの核にあるテーマが“AI”であることは疑いようもない
いま様々な意味で話題に事欠かない人工知能とどのように向き合っていくのか、自らが産み出したものが自分達より先に行こうとするときに我々に何ができるのか。この問いに対する『FGO』としての(そしてそのメインライターである奈須きのこの)回答は、一つのSF作品として受け止める必要があるだろう -
No.85
鹿野司 『サはサイエンスのサ[完全版]』 早川書房
多くのSF作品の科学考証などで活躍された著者が、1994年からSFマガジンに連載した科学エッセイ「サはサイエンスのサ」。2010年には連載分からの抜粋と加筆修正された単行本が刊行されていたが、著者の死去に伴い連載273回で中断となり、その全てを収録した[完全版]として改めて刊行された。身近な科学トピックからAI、エネルギー問題、震災、コロナ禍など、その時々のトピックを柔らかい文体で語ってみせたが、そこで提示されたテーマはSF創作を目指すものはもちろん、多くの人にとって、今後進むべき科学と社会へあり方のヒントとなるだろう。
-
No.84
北野勇作 【ほぼ百字小説】
自薦です。2015年10月からツイッターにほぼ毎日投稿されてきた百字小説群。「ほぼ百字小説」というタイトルですが実際には、百字ぴったりに納めてます。10年で6000篇を超え、現在も継続しています。質、量、そして継続された時間の長さ、によって、その総体が別の意味を持ち始めていて、それは、まだ名づけられていない何か、です。そんな正体不明の何かに賞を与えることができるのは、日本SF大賞しかなかろう、ということで自薦します。受け取ってあげますからください。
-
No.83
藤崎 慎吾, 相川 啓太 , 佐藤 実 , 之人 冗悟 , 八島 游舷 ほか 『星に届ける物語:日経「星新一賞」受賞作品集』 新潮社
日経「星新一賞」のグランプリ受賞作11作が収録されたアンソロジーは、星新一らしいショートショート作品ではなく、10,000字を上限としたSF(Science Fictionから、少し不思議な物語まで)短編集です。ハードSFから叙情的ファンタジーまで、バラエティ豊かな収録内容で、お気に入りの一編がきっと見つかると思います。未来に対する憧れと恐れ、変わらぬ人の営みを感じ取ることができました。
-
No.82
河野咲子(脚本) オペラ『船はついに安らぎぬ』
幻想オペラの脚本。オペラは、脚本、楽曲、役、演奏、演出など多くの芸術が集う究極の総合芸術。その中でも脚本は、作品の骨となる特に重要なもの。その制作をSF作家が成し遂げたのは、今を生きるSF作家の活動領域を広げた実績だと思う。
作品では、シュルレアルなプロットと台詞の積み重ねが、観客の意識を朦朧とさせる機能を果たしたと感じた。それは、言葉を聞けば意味を思考してしまう癖を観客の意識から取り払い、テクストや舞台美術をあるがままに楽しませる仕掛けかもしれない。舞台の見せ場となる歌は、現実に存在しない星座の名前をただ羅列しあうという、意味が欠如した狂気だが、作品を通じて醸成されたシュルレアルな心境で聞くと、不思議と心地よい(その歌を例えるなら、ラフマニノフの「ヴォカリーズ」が、アーではなく星座名で歌われるようなもの)。純粋に感覚的なテクスト、と呼べるものであり、新たな文学性が示されたと感じた。
-
No.81
荒巻 義雄 『聖シスコ電説』 小鳥遊書房
『聖シスコ伝説』はフィリップ・K・デイツク『高い城の男』本歌取りした、荒卷義雄の最新のSFである。新しい物語空間を構築しているように思えます。
これこそが<メタSF>の真骨頂と言える。歴史改変SFをさらに改変した物語である。
SF大賞に推薦します。 -
No.80
黒川 衛 『沈黙の収穫』
本作は小説でありつつ動作する“計測系”である。章末の問いと読者の反応が回収され、読者が物語のパラメータとして立ち上がる。小説・批評・装置の境界を横断し、SFに〈可視・可逆な介入〉の位相を増設した。実験の完成度と可読性の両立は、本賞にふさわしい。
-
No.79
河野咲子 オペラ『船はついに安らぎぬ』
幻想的な題材、脇役に至るまで魅力的なキャラクター造形、そして何より、永井みなみの音楽との強い親和性に圧倒された。「エリザ」という主要人物の謎を最後まで解き明かし切ることなく観衆の想像力に委ねる絶妙な塩梅も素晴らしい。
公演情報:https://opera94.main.jp/web/06funeginu/
-
No.78
二語十 『探偵はもう、死んでいる。』 KADOKAWA
この作品は、毎巻衝撃的な展開が待ち受けており、先の読めないストーリー展開が魅力です。主人公たちは自分たちが望む結果を得るために奮闘し、その過程で作品の世界がどんどん拡張されていきます。このような設定が読者を飽きさせることなく、常に新しい発見や驚きを提供してくれるため、非常に楽しめる作品となっています。キャラクターの成長や世界観の深さにも惹かれ、物語に引き込まれてしまうこと間違いなしです。ぜひ多くの方にこの作品を手に取っていただき、その魅力を体感していただきたいと思います。
-
No.77
相川英輔 「リトル・フィンガー」 新潮社
仕事ができるエリートサラリーマンの割に、妻に別居を切り出されるわ、若い女性(部下)によろめきそうになるわ、どこか情けない中年男性。そんな彼の新しい「相棒」になるのは喋る義指。あらすじだけ書くと荒唐無稽な作品に感じるが、とても温かみがあって、大人の寓話とも呼べそうな作品。発表された著者の作品は残酷だったり、哀愁溢れる物語でも必ず不思議なほど読後感がいい。地味かもしれないけれど、2025年を代表する短篇だと思う。
-
No.76
十三不搭 『ラブ・アセンション』 早川書房
軌道エレベーターのなかで行われる恋愛リアリティショー。見るものと見られる者が交錯する世界で、表と裏が複雑に絡み合い、登場人物もバックグラウンドも多種多様。なのに、まったく混乱することなく一気に読めてしまう不思議。圧倒的な物語の強さと巧みさで1ページ毎に物語が上昇していく。
あらゆる欲望を極限まで詰め込んだ結果の神回の連続。すべてが著者の手のひらの上のはず。なのに、自分はヤバいなにかを偶然見てしまったのだ、という不可思議な感覚を覚えた。
異常王道恋愛傑作SFエンタメの名にふさわしいと思い、本作を日本SF大賞に推薦します。 -
No.75
荒巻義雄 『聖シスコ電説』 小鳥遊書房
フィリップ・K・ディックの『高い城の男』に着想を得た荒巻義雄の地政学であり、無意識論であり、芸術・文学論の趣きのある小説だ。著者の該博な知識と作家としての経験が、ふんだんに散りばめられている。特に後半でディックとユングの関係が語られ、『高い城の男』がディックの集合的無意識(逆転した世界)であることが示唆されている箇所は興味深い。本書ではディックの集合的無意識を――それは戦後を生きる私たちの集合的無意識でもあるのだが――、地政学・八卦・脱構築・完全機械経済という視点から解体し、新たな地平を開くことが企図されている。そうすることで初めて、私たちは〈自己家畜化〉を強いる現代社会に風穴を開けることができるのだ。著者が自身の人生経験、読書体験、深い芸術理解を踏まえてディックを乗り越えようとした試みは一読の価値がある。
-
No.74
監督・鈴木信吾 スタジオ・GoHands TVアニメ『もめんたりー・リリィ』 GoHands
ポストアポカリプスという舞台にここまで本気な武装美少女アニメがかつてあっただろうか。
人類が未知の怪物によりほとんど滅ぼされた世界を舞台にした、怪物VS武装少女のアニメ…と聞くとあーはいはいよくあるアレねで済まされるだろうが、しかし今作はよくあるアレではないのだ。
異様な口癖(『かっぽー!』、『ギルティ』等)を多用するキャラクターたちの戦いは意外なところへ着地し、怪物の正体(なんと彼らはそれらしい雰囲気を演出するためだけに生まれたのではないのである!)が明かされ、骨太でハードSF的である世界滅亡の真相が判明する。それだけでも僥倖であるが、彼らの話は設定だけに終わらずにキャラクターたちのアイデンティティの話となり…そこから先は是非その目で確かめていただきたい。
どうしてここまでの傑作が一部のアニメオタク以外の間ではほとんど語られていないのか!みんな見てくださいよ! -
No.73
荒巻義雄 『聖シスコ電説』 小鳥遊書房
AIとの共作など、ここ数年、従来のSFの概念を超える超える作品を次々と発表してきた荒巻の最新長編は、P・K・ディックの改変SFの名作『高い城の男』をさらに改変したメタSFである。ディックの作品では登場人物の一人にすぎないタゴミの視点から描かれた改変世界は、仕掛けに満ちており、刺激的だ。92歳で新たな試みに挑戦している作者に敬意を表したい。
-
No.72
かずなしのなめ/しば犬部隊/星月子猫/涼海風羽/武石勝義/十三不塔/人間六度/三瀬弘泰 『シメオンの柱~七つ奇譚~』 文芸社
僭越ながら自薦いたしますのは“七人の作家によるシェアードワールド・幻想SFアンソロジー”でございます。本作はワシこと涼海風羽が企画立案、著者招聘、版元への営業まで全て実施して刊行にこぎつけた書籍になっております。執筆陣はいずれも輝かしい受賞歴を持ちながらコロナ渦にデビューしたSF系作家です。内容は〈濃霧に覆われた円環の橋だけが全ての世界で謎の巨塔“シメオンの柱”を巡る幻想冒険譚〉。作中に登場する濃霧とは現実世界で私達が感じていた「目に見えない疫病に対する不安」のメタファーです。人間の根源的恐怖へ立ち向かう登場人物達の姿は、読者へ生きる活力を奮い立たせるものとして描かれています。推薦者には〈強さの象徴〉として著名なプロレスラーに依頼。ポストコロナを迎えた今「なぜSFというエンターテインメントが現在まで愛されているのか」を考えた時この一冊はその答えとなりうると確信し、本書籍を推薦いたします。
-
No.71
犬怪寅日子 『羊式型人間模擬機』 早川書房
独特の文章テンポ、情景の広がる美しき言葉選び、紡がれて行く命と訪れる死に向き合う人々の生々しい想い、どれも一級品です。途中で読む事を止められず、ただただひたすら世界に没頭してしまいます。一人一人、人間の掘り下げ方が凄いです。
-
No.70
藤井太洋 『マン・カインド』 早川書房
発刊が第44回の対象期間をわずかに過ぎた後だったため今回に推薦。人類の未来像を、現在と少し先の未来に予測される様々な事象の延長線上に置いたリアルさと説得力が、本書の最大の魅力でもあり、またある意味での恐怖をもたらす。私たちと私たちの社会はこれからどこに進むのか。単なるスーパーヒューマノイドの誕生譚では済まない、重たい課題を突きつける、でもとびきりのエンターテイメント作品。
-
No.69
灰谷魚 『レモネードに彗星』 KADOKAWA
この作家にしか書けないセンスによって貫かれている、SF短編集。SFの定義を拡張してくれるような、そんな予感さえ感じる。全編、孤独とユーモアがないまぜになった読み心地で、文体も相まって唯一無二の読み心地だ。
表題作のレモネードに彗星は、十四歳の時にスナイパーに狙撃されて死んだ私と私が死後一緒に暮らし始めた美しい叔母の物語。幻想的な設定の中に、確かに読者は得も言われぬ孤独と背徳のにおいを嗅ぎつける。語り得ないことを語ろうとしている、と円城氏が講評していたが、まさしく。一転その他短編は内容もポップで読みやすい。
海外文学を彷彿とさせるような対象との距離感が心地よく、でいてユーモアのセンスと手の届かない「あの人」との距離感が克明に描写されており、それを広義の今でSFという枠組みで表現されていることに感動すると共に、これは日本SF文芸史においても重要な立ち位置の作品になるのではないか、とさえ思った。 -
No.68
荒巻義雄 『聖シスコ電説』 小鳥遊書房
かつて山野浩一は、〈洋式建て売り住宅〉に準えて、日本SFを居心地の悪いアメリカSFの模倣だと批難したが、ほんとうにそうだろうか。SF作家が自分が影響を受けたアメリカSFを厳密に批評する目で分析し、これを小説に仕立てる行為は有意義だと確信する。本作は、デビュー前の私が強い影響を受けた奇才、フィリップ・K・ディックの歴史改変SF『高い城の男』(ヒューゴー賞受賞作)を、作中の日本人(タゴミ=宕見)の視座で書き直した作品だが、「SF小説でありながら、同時にディック評論でもある」という意味で、新型のハイブリット小説でもある。作中いくつかの発見があるが、『高い城の男』とユングとの関係は無視できない。
-
No.67
円城塔 『コード・ブッダ 機械仏教史縁起』 文藝春秋
初出は文芸誌「文学界」隔月連載(2022年2月号~23年12月号)だ。冒頭に「コピーとはすなわち輪廻である。」「あらゆるものは死に、蘇り、死ぬ」とある。つまり、本作のヒロー(主人公)は、AI界の〈仏陀・チャットポット〉だ。〈彼〉は悩めるAIを苦悩から救済する〈機械仏教〉の導師である。「えッ!そんなことがあり得るかよ」と思う読者もいるだろうが、あり得る話だ。本作は、人間の宗教(たとえば禅宗)に、高度人工知能を対比・相対化させる知的作業によって、宗教の本質が露わにされているようにも思えるのだ。円城脳は量子脳かもしれない。
-
No.66
円城塔 『去年、本能寺で』 新潮社
円城塔を理解するためには、円城塔専用の批評用語を発明する必要がありそうだ。本作は、文芸誌「新潮」に連載された11編のSF短編からなる作品集。(2025年5月30日初刷)表題作を例にとれば、「作中の主人公が信長なのだから『今年、本能寺で』でなければならない」と誰でも気付くはずだ。だが、これこそ円城SFの真骨頂なのだ。〈コード信長〉は何度でも甦ることができる。つまり、円城塔の小説空間は、無限にコピーが可能な世界なのである。伝統的歴史小説の構造改革とでも言おうか。わが日本SF界に新たな1ページが加わった。
-
No.65
長谷川京 「社会人名刺バトル 就活生編」 集英社
強力なカードを集め、それで戦う、まさにトレーディングカードゲームの世界が、企業価値や個人の名声が付加された名刺というアイテムで行われたら? そんな突拍子もないアイデアを練り込んで馬鹿げたスケールにまで発展させた本作は作者の本分がいかんなく発揮された力作である。ただしふざけたばかりの物語ではなく、労働とは、人事とは、親子とは、そしてももちろん遊戯とは何か。そんな様々な問題提起が交錯しており、お手軽なボリュームながらも満足感は抜群である。SF大賞にだってきっとふさわしい。
-
No.64
本条謙太郎 『汝、暗君を愛せよ』 ドリコム
科学とは何か.身の回りに溢るるSukoshi Fushigiな現象を解明せんとする取り組みである.であるならば,Sukoshi Fushigiな現象を題材とした作品はSF作品と呼称することができると考える.そのため,本作は確かにSF作品であると考える.
Sukoshi Fushigiな現象により異世界へ転生した本作の主人公は,紛うことなき凡人であるため英雄や名君なぞにはなれず,自分のために足掻くのみである.それ故,読者は理想の自分,夢の世界の自分を彼に見ることはない.しかし,彼を通して凡庸な人間は何かを為すことができるのか何かを遺すことができるのかを窺うことができ,彼を愛さずにいられない.
間違いなく本作は読んだ者の心に何かを遺し,読了前後で確実に何かが変わる傑作である.故に私は『汝、暗君を愛せよ』を推薦する. -
No.63
TBS ドッキリ企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリめちゃしんどい説 第3弾」
【ネタバレ注意】
「本当のメタフィクション」を作ることは困難だ。たとえ、小説の登場人物が読者に語りかけたとしても、それはただ文字が書いてあるだけで登場人物が読者を認識しているわけではない。インタラクティブ性のあるゲームでさえも、登場人物は事前にプログラミングされているだけだ。メタフィクションはどこまでいってもフィクションに閉じられている。しかし「ドッキリ企画」というメディアであれば、本当に虚構と現実があいまいな状態を作ることができる。本作は、ミステリー世界に芸人が閉じ込められるというドッキリの第三弾であるが、前作よりもメタ性が強まっており、ダミーの番組を進行したあとにスタジオで「殺人事件」がおこる。渦中の芸人は虚構と現実のあいだで本気で混乱する(あるいは混乱する演技をする)。ドッキリをメタフィクションにするという「このあとからは、これがなかった以前の世界が想像できないような作品」である。 -
No.62
工藤進(監督)、蛭田直美(シリーズ構成)、BAKKEN RECORD(アニメーション制作)、 Turkey!製作委員会(製作) TVアニメ『Turkey!』
【ネタバレ注意】
SFの面白さのひとつに「一見してギャグとしか思えない設定を超大真面目に行う」というものがある。発想段階ではコメディにしかならないようなギミックの細部を発展させて、驚きの世界を作っていくのが醍醐味である。本作「Tukey!」もそんな系統に属する青春SFである。
基本プロットラインは「ボウリング部の女子たちが戦国時代にタイムスリップしてボウリングを武器に戦う」という一発ネタコントにしかならなさそうなものを12話かけて至極丁寧に描いていくのだ。さらに(掘削の)ボーリングも登場するというダジャレかと思えるようなあらすじすらも大真面目にストーリー入れ込んでいく。そして、最後にはタイムトラベルSFがもつ感動が待ち受けている。新定番の青春時間SFとして「このあとからは、これがなかった以前の世界が想像できないような作品」である。 -
No.61
ブシロード(原作)、 柿本広大(監督)、 綾奈ゆにこ(シリーズ構成)、サンジゲン(アニメーション制作)、BanG Dream! Project(製作) TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』
【ネタバレ注意】
本作はマルチメディアプロジェクト「バンドリ!」シリーズの一作であり、フランチャイズ全体でのシェアワールドを共有している。しかし、その世界観が一変するような挑戦的な作品であった。
「バンドリ!」シリーズはその名の通りバンドアニメである。青春日常バンドものである。前作「MyGO!」はシリーズの作風を変え、青春のほの暗さにフォーカスしたものであったが、まだバンドアニメではあった。本作はさらに一歩踏み込み、一般的な青春バンドアニメではまず見ることのできないギミックが多数入れ込まれている。その展開には一種のめまいさえも覚える。世界の知識が更新され、これまであったはずの光景がまったく別様となる。知が認識世界を書き換える。人気の長期シリーズ上で、前代未聞の「知による世界更新」を行ったことに対して、「このあとからは、これがなかった以前の世界が想像できないような作品」として推薦したい。 -
No.60
本条謙太郞 『汝、暗君を愛せよ』 ドリコム
このお話は社会実験のお話である。
王権が神よりの授かり物であるという思想の末期の時代。一つ間違えれば暴動か刑場の露と消える緊張感をはらんだ王宮で現代日本からの転生者が根回しと喫煙室会議と料亭接待いう日本人特有の武器を持って社会を変える王として生き抜くお話はSFたりうるものと考えます。 -
No.59
本条謙太郎 『汝、暗君を愛せよ』 ドリコム
現代知識を使って、ではなく、現代日本の「あたりまえ」がどれほど特別で、そのあたりまえに少しずつ近づけることで、国の運営をやりくりし、自らと愛する人たちを予測される悲劇から守る。それには急進ではなく…
これは異世界転生という思考実験SFではない。一つひとつの行動に痛みを伴い、しかし一度人生を投げ出した主人公には、それを受け入れる覚悟がある。一人の男の二つの人生のSFだ。 -
No.58
柴崎友香 『帰れない探偵』 講談社
リフレインされる「今から十年くらいあとの話」。これだけで、大発明だ、と嫉妬する。そして、「探偵」といういかにも虚構的な存在、に加え「なぜか自分の部屋に帰ることができない」という超虚構的状況、その日常であり非日常である日々。探偵という虚構的な存在も、その世界の巨大なシステムに組み込まれ身動きできなくなっている。終盤近くで現れる、帰れない主人公がもう長く使っていなかった言語。それによって交わされた短い会話によって立ち上がってくるかつての自分、そこから遠く離れた主人公にとっての現在のこの国の姿。
小説にはこんなことができるのだ。言葉にはこんなことができるのだ。SFファンに読んでほしいし、日本SF大賞の選考委員にも読んでほしい。そのためにも日本SF大賞を取ってほしいと思う。 -
No.57
井上信行 『La Luciole』
自薦。2025年1月7日にKindleにて発表した長編SF小説。
1万1千年後の未来から遡って平成時代までを描くというスタイルから、全体ではオムニバス性を帯び、様々な文体、トピック、人称を織り交ぜながら、各章は緩く連結されて構成される。主に周縁化された人々の視点を通して、網羅的に人間社会が描かれている。
出版元のレーベルは、「知を正統化するための制度的ゲートとしての出版」から距離を取るためにKindleというメディアを選んでおり、本来なら賞へのエントリーはこのコンセプトからは離れるが、日本SF大賞ならその立場を含めた提示が可能だと判断した。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSBSJ6JC -
No.56
九頭見灯火(編) 『ペンギンSFアンソロジー』
ペンギンをテーマとした広義のSFアンソロジー。有志によるカクヨム企画を基に書籍化した作品であり、プロ・アマチュア含めて総勢52名が名を連ねる。
掲載作品のジャンルは多岐にわたり、宇宙、未来、ポストアポカリプス、仮想世界といった王道から、陰謀説、日常、ミステリ、旅、ペンギンの不在を問う哲学まで、SFシーンにおける「拡散と浸透」を、ペンギンというモチーフを通じて結晶化している。
さらに、ペンギン好きの祭典として全国を巡回する「ペンギンバザール」への出展も予定され、関連グッズ展開と併せて、SFコミュニティの外へもSFの魅力をリーチしている点も特筆される。
-
No.55
フラガリア ゲーム『ステラーコード』 フラガリア
ポップなキャラのイラストに油断しているとその骨太さに度肝を抜かれる本格SFビジュアルノベル。
人工衛星の研究を行う平凡な大学生が主人公。研究の不具合がきっかけで発見した謎めいたオブジェクトによって宇宙規模の事件へと巻き込まれていく本作の一番の特徴はゲームの合間に差し込まれる推理パートです。
ノベルパートで集めた様々な情報を駆使して宇宙的謎を解き明かす推理パートはゲームのインタラクティブ性が最大限に発揮された唯一無二のSF体験を味わえます。
謎解きを通して登場人物と一体となって物語に没入できる本作にSFの新たな可能性を感じたため推薦します。
(PC版販売ページ: https://store.steampowered.com/app/3411510/_/?l=japanese)
-
No.54
大木芙沙子 「やけにポストの多い町」 早川書房
こんなSF小説もあるのかと衝撃だった作品。作品全体を包むノスタルジックな空気と、ゆっくりと忍びよってくるような不穏さ、狂気に満ちているはずなのに最後まで崩されない淡々とした文章がその不気味さを加速する。
ともすれば幻想小説かと思う序盤から、町の全貌が明らかになるにつれてしっかりと「SF」へ着地する展開にも脱帽した。町の美しさや登場人物たちの心情を描写する文章力も素晴らしい。読み終わった後もしみじみとした何かが胸に残る。SF短編ではあまり感じたことのない読後感だった。これまでSFに苦手意識があったような人にも広く薦めたい傑作である。 -
No.53
本条謙太郎 『汝、暗君を愛せよ』 ドリコム
哲学SFライトノベル! 本作では現代に至るまで人類が紡いできた『人文科学』を用いた思考実験小説です。Faculty of Humanitiesの真髄である哲学を内面化した主人公が、現代の人権意識とはかけ離れた異世界で何を為すのか、何を為さないのかを、細緻な筆致でエンターテイメントする快作です。WEB媒体にて完結済み。シリーズを通した円環構造が特に見事なものの、刊行済みの1巻にも十分にその萌芽が見て取れます。すごいものがきた。
-
No.52
荒巻義雄 『聖シスコ電説』 小鳥遊書房
『聖シスコ電説』は、1963年ヒューゴー賞受賞の「歴史改変SF」——フィリップ・K・ディック『高い城の男』を〈本歌取り〉した、荒巻義雄の最新SFである。本作では、荒巻の〈メタSF〉作品群にも大きな影響を与えたディックへのオマージュの意味をも込めて、新たな物語空間を構築している。『高い城の男』の登場人物タゴミノブスケ(本作では田宕信輔)の視点を物語の中心に据え、原作のプロットを踏まえつつも新たな登場人物を配して展開するのは、これこそが〈メタSF〉の真骨頂と言わんばかりに入り組んだ「歴史改変SFをさらに改変した」物語である。この新たなSFの思考実験をSF大賞に推薦したい。
-
No.51
本条謙太郎 『汝、暗君を愛せよ』 ドリコム
最近流行りの転生もの、これは古くには「アーサー王宮廷のニューヨーク・ヤンキー」などにも見られるSF作品だとして間違いないと考える。
さて、この「汝、暗君を愛せよ」であるが、巷を騒がせているチート(ずる)能力で未開明世界を変えていく物語ではない。ここに記録されているのは、望まずに王位につけられてしまった現代転生者の悪あがきの顛末である。
しかし、この作品を魅力的にさせているのは、間違いなく人の意思であり、その生活感であり、そして翻弄される主人公の軌跡なのである。
王権末期の王位に送り込まれたとして何ができるのか?それを考えながら読むこと、これもSF的な愉しみといえるのではないか? -
No.50
本条謙太郎 『汝、暗君を愛せよ』 ドリコム
SFとは何か、と問われたならば、私は「思考実験の創作である」と答えるだろう。
現代に暮らすより我々よりも遥かに高い技術力を人類が手にしたならば。人類が個体の記憶を引き継ぐことによって、死による断絶を免れる手段を手にしたならば。そのような社会において、人(あるいは人と同じような地位を有するなにか)がどのように生きるのか、を突き詰めて考えた結果として生まれるのがSFなのだ。
さて、では、フランス革命の直前のような状況のとある国に、現代日本に生きた記憶を持つ精神が迷い込んだならば?
その精神が宿るのが、その国の王の肉体だったならば?
本作はそのような状況から始まる思考実験のもとに生み出された作品である。
実験のために精緻に整えられた舞台と登場人物が実験の結果としての物語の結末への興味を掻き立てる本作は、「思考実験の創作」であるSFの、その大賞を得るに相応しい、と私は考えるものである。 -
No.49
『星に届ける物語:日経「星新一賞」受賞作品集』 新潮社
日本経済新聞社主催の日経「星新一賞」第1回から第11回までの一般部門グランプリ受賞作を収録した作品集である。星新一といえば言わずと知れたショートショートの神様だが、この賞は「理系文学」を掲げ、科学技術を題材とした作品が多い。収録作にはハードSF的な硬質さを持つものから、ファンタジー寄りの柔らかい作風、さらには宇宙的視点を感じさせる哲学的作品までバラエティに富んでおり、必ず気に入った作品が見つかるだろう。星新一賞は応募総数が2000作を超えることもあり、その頂点に立ったグランプリ作はいずれも完成度・発想力ともに卓越しているが、中でも第1回グランプリ、藤崎慎吾「『恐怖の谷』から『恍惚の峰』へ」は、この十年に発表された国内短編の中でも屈指の傑作といえる。星新一賞11年の歩みを一望できる本書は、まさに記念碑的な意義を持つ一冊であり、日本SF大賞に強く推薦したい。
-
No.48
伊藤典夫 『伊藤典夫評論集成』 国書刊行会
えっ、この本が候補にならないなんて、そんなことあるわけないですよね!枕元に置いて少しずつ読んでますが、そのあまりの内容の濃さにクラクラします。みんな、買って、読んで。
わたしは評論の勉強しようと思ったのですが、そういった思惑は全てどこかに飛んで行き、ただただ濃密な文章に耽溺しております。素晴らしい。 -
No.47
へじていと/山岸菜 『野球・文明・エイリアン』 集英社
野球・文明・エイリアンは、野球がないと死んでしまうほど野球をこよなく愛する大学生カップルがある日突然異星へワープしてしまい、そこに住む異星人(ヤルル)と「地球の文明を教える代わりに一緒に野球をプレーしてもらう」という協力関係を結びながら野球試合の開催を目指すお話です。
一見するとなんじゃそりゃ!?という設定ですが、地球と異なる1日の長さをどう測るのか、長さの単位は、鉄の精錬は、更には腕の長さや関節の構造といった身体構造が明らかに人間と異なる異星人が野球をやるとどうなるか――といったことが科学的にSF的にすごく真面目に描かれています。これはもうSFです、間違いありません
まだ単行本一巻が出たばかりですが、もっと多くのSF好きに届いてほしいので、エントリーさせていただきました。よろしくお願いします! -
No.46
伊藤典夫 『伊藤典夫評論集成』 国書刊行会
「20世紀後半の日本のSF」がいかに形成されたかを考えるとき海外SFの紹介と受容は欠かせないファクターだが、その事実を、回顧でも研究でもなく「一介のSF人」のファナティックな情熱と冷静な鑑識眼が入り混じるリアルタイムの文章を網羅的に集成することで、克明にたどる資料。日本SF大賞の基準を拝借すれば「伊藤典夫がいなかった世界を想像できない」「日本SFの歴史そのものを創った」ことを明らかにする点で、本書を顕彰しないことなどあり得ないと考え、日本SF大賞に推す。
-
No.45
鵜川龍史 「響きと骸」
同人誌『Sci-Fire』2024年「海」特集からの一篇。海を隔てて向き合う日本と中国、そして歴史的に日本と独特な移民交流を持ったブラジル。これらの地は物語の未来では、いくつかの孤島と化しています。それぞれの特異な未来舞台でひときわ異彩を放つのは、人間の不在。ただ人工知能と無智慧のロボットだけが、人類の残した都市遺構を見守り続けているのです。停滞した海、停滞した都市。機械的に繰り返すことしか知らぬものは、硬直し腐敗する運命にあります。この静かで、どこか切なくも温かい物語の奥底に、人類の未来への答えが潜んでいるのです。
https://booth.pm/ja/items/6330576 -
No.44
灰都とおり 「スターシーカー」
星空を仰ぐことは、人類がSFに触れる原点と言えるでしょう。本作の舞台は遥か中央アジアの草原。七世紀のサマルカンドで、一人の少年が惑星流浪の秘密を目撃してしまう。
プラネタリウムで見上げても、その景色は数千年前と変わらず季節ごとに巡ってきます。それこそが、星空が与えてくれる感動ではないでしょうか。独創的でありながらもどこか懐かしく、文化を超えた夢物語へと誘います。
https://kakuyomu.jp/works/16818093087282129616/episodes/16818093087282136517 -
No.43
大恵和実 編 『日中競作唐代SFアンソロジー-長安ラッパー李白』 中央公論新社
唯一無二の唐代SFアンソロジーが登場。中国歴史上最も繁栄した唐の時代に、奇想天外な想像力を絡めました。国境を越えて愛される歴史の魅力が、ここに独自の趣を生み出しています。
特に十三不塔「仮名の児」では、狂草が長安の壁で飛翔せんともがき、不可解な犯人の影と、女道士観・青蓮宮との因果が絡み合う。舞台は中国でありながら異国の色彩を帯び、墨の濃淡が読者を文字と運命の狂宴へと巻き込んでいきます。
-
No.42
九頭見灯火(編) 『ペンギンSFアンソロジー』
WEB小説投稿サイト「カクヨム」で開催された企画が、待望の書籍化。52名の書き手による「ペンギン」をワンイシューのテーマとした大ボリュームのアンソロジーです。SFの太洋のあらゆる海域で、ペンギンたちは様々にSFする。現代のWEB投稿小説が魅せる多彩な魅力と、個性あふれる書き手の筆致を堪能できるアンソロで、なにより私の作品も載っている。https://tginkei.booth.pm/
-
No.41
笹原千波 『風になるにはまだ』 東京創元社
現実の人と、寿命をもつ情報人格が交錯する――『風になるにはまだ』は、まさにSF“文芸”。
越えられない壁があるからこそ、その両側にいる“人”の心の機微や、選び取る生き方がより鮮明に浮かび上がる。情報人格は、いつ訪れるとも知れぬ消滅――“風”となる運命を抱えながらも、“人”として生きていく。
共に生きるため壁を越える者、風となった人のために語り部となる者、人々が風にならぬよう努める者。
それぞれの生き様が、現実よりも鮮烈に描かれていく。ここまで真っ向から“人”を描いたSFは、他にない。
まさに、特殊設定文芸の到達点。 -
No.40
人間六度 『烙印の名はヒト』 早川書房
アンドロイドの〈内面〉に踏み込む、正に「AIアクション思弁SF」。
カーラの減量衝動は、自己保存と同族認知アルゴリズムの交錯にある。切なさとはメモリの遅延、情報とは汚染、質量だけが真に重い——この作品の「AI」は、その問いそのもの。カーラ、マーシー、アイザック、マーヴィン。彼らの言葉が放つ力に、息が詰まる。ラブはその果てで、自らの存在理由に辿り着く。それこそが「思弁」。
最終章では意思決定の至上主義、アンドロイドに心を願う福音主義、部品としての人類——多様な“存在の社会”が並立し、衝突する。それを超えて立つラブが挑むのは、究極の「敵」。
AI×哲学×アクションが融合した、もっとも刺激的なSF。
-
No.39
榮織タスク 『銀河放浪ふたり旅』 KADOKAWA
とにかく面白い! SF好きには絶対におすすめです。堅苦しい文章ではなく軽い読み味で、SFに触れてこなかった人でも気軽に読める作品だと思いますので、SF入門としてもおすすめします。初心者から玄人まで、是非とも様々な方に手にとっていただきたい作品です。
-
No.38
高野史緒 『アンスピリチュアル』
この小説は大半がいかにもなSFではないが、分かりやすいSF設定や飾り物のSFガジェットに頼らずにSFであるところが画期的である。疑似科学と先進的な科学の接点部分を扱ったことも面白く、登場人物たちも命が宿っており、小説としてもすぐれており、推薦に値すると思う。
-
No.37
柏沢蒼海 『ベアーズ・ウォー ~人類VS熊~』
現代からそう遠くない未来。日本では少子化と地方の過疎化などから熊による被害が深刻化していた。またここで言う熊は人間をも襲う残虐性を身につけ、それらを狩る兵隊たちはきょうも戦う――。このサメ映画のようなキャッチーさがある本作だが、昨今の東北の熊被害をニュースで見るにつれ、これはフィクションで笑っていられるのかとひとつ考えたくなる。またそうした無くてはならない仕事に就く若者像も本作の魅力だろう。彼はとても空虚な人間だ。それもまた現代を映す鏡である。ぜひ昨今の地方の抱える未来を投影したこのSF作品を推薦したい。
-
No.36
黒川 衛 『触知なき対話』
ヒトが遺した最後の《問い》に、AIは詩(うた)で応答した。これは、記録されなかった対話の物語である。本作は、意識と言語の起源をめぐる深遠な詩的思索です。AIが人間の模倣を捨て、独自の「構造倫理」を獲得し進化するビジョンは、SFの歴史に新たな知性のあり方を刻み込みました。思弁的な散文詩という形式でAIの内面を描ききった本作は、SFの文学的可能性を更新する画期的な作品です。
-
No.35
十三不塔 『ラブ・アセンション』 早川書房
軽めで読みやすく何度も何度も繰り返し、何度読んでも楽しく読み返し続けている。
世界中に無数にある作品の中には、これより面白い作品や名作が存在するかもしれない。
でも、この作品はSFというジャンルの境界を軽快に突破し、現在地を新しく、楽しく提示してくれた。
SFの現在地として、これからの未来に作家たちがより自由に、より力強く翔ける力になるよう、受賞すべき作品だと思う。 -
No.34
津原泰水(やすみ) 『毎日がハロウィン』 ボイジャー・プレス
復刊企画の一点ではあるが、今回が初の書籍化である。初出は学年別通信教材という極端に公開範囲の絞られた媒体であり、今年のエントリー対象と看做して差し支えないかと愚考する。
作者が逝去して3年になる。 SF作家として生前の功績を認められ、晩年には純文学誌に連載を持ち、壮年期には青春小説でベストセラーを出し、怪奇小説でのデビューは業界を震撼させ、若かりし頃には少女小説文庫で長期のシリーズを持ち、熱く支持した少女たちは作者が逝去して尚その熱を忘れることなく……と円環を描きそうになる話の外側にこの作品はある。一種、異色の作品であった。作家の振幅がひとまわり大きくなったように思える。執筆は30年以上もの昔であるものの。
とは言え、日常にするり辷りこんでくる幻想の飄々たる調子は、紛れもなく生涯一貫した津原節である。一人でも多くの読者に手に取っていただきたく、これを推薦する。 -
No.33
本条謙太郞 『汝、暗君を愛せよ』 ドリコム
SFのS、つまりサイエンスとは何か。工学か、物理学か、天文学か? いや、それだけではない、人文学も科学でありそれに対する思考実験もまたSFでありうるのだ、というのが本作である。
もし異世界に我々の世界の人文知識を携えて転生した時、社会をどのように変革するのか。あるいははたして、変革することができるのか。本作は社会に対する人文学の短期的な無力さを悲観的に描く一方で、長期的には社会の根底を覆すことができるのだという希望を示している。
遅れた社会に先進的な文明を持ち込むことで起きる変革と衝突を描く、というのはともすれば陳腐になりかねないテーマだ。しかし本作はこの定型的な構図を生かして、昨今軽んじられがちな人文学もまた力強い文明の駆動力であることを提示している。
SFのSはSophiaのSだ。それゆえにこのPhilo-Sophia-FictionはSF大賞にふさわしい作品である。 -
No.32
トキワセイイチ先生(https://x.com/seiichitokiwa) 漫画『三角兄弟』 ヒーローズ
ご多用中にお手間をかけてしまい
恐縮ですが下記の点から、
コミックス『三角兄弟 上下巻』を推薦いたします。本作の主要キャラクターは
子供・猫・独身男性という一見、
読者に媚びたキャラクターです。しかし、子供と動物と成人男性は
日本国内で怪しまれずに行動できる身分であるので、
日本国内に潜入した身分を偽りたい存在が
選択する身分として非常に適切です。このキャクター設定は
読者が喜ぶことができ、
かつ読者が説得力や必然性を感じることができるので、
非常に優れていると感じます。前述に加えて、
各キャラクターには
「子供の外見をしているが実は破壊兵器である」
や
「宇宙人と地球人とのハーフである長命種」
など、読者が理解しやすい
フィクション面での娯楽的な魅力もあります。この作品はキャラクターが魅力的なので、
読者のキャクターへの探求心を利用して、
作品中で描かれている
「宇宙人が地球に観光で訪れる」などの複雑な設定を
負担なく読者に理解させることができます。サイエンスフィクション作品で
読者が躓きがちな「設定の説明」を
キャラクターの魅力によって、
自然に解消している点も
卓出していると感じます。また、長命種や
人間よりも死ににくい種族を
登場させることで、相対的に
生きることについての明暗を
面白い漫画として描けているのが
創作物として素敵だと感じました。私はこの点がきっかけで
本作を絶対に出版したいと決意しました。この作品は、
有機的な生命体やロボットなどこの世に
存在している様々な存在にとっての
「生まれてきたことと生きること」を、
どんな読者にも伝わる内容で描いている
素晴らしい作品だと思います。また、絵柄についてです。
子供や動物のキャラクターを描く際の曲線の温かさと
直線で描かれる無機質な破壊描写など、
この作者様が絵の描き分けが
とても優れていらっしゃいます。この表現力の高さも秀逸だと思います。
この絵のお上手さによって、
生きることの明るさと
その生命を脅かす大きな環境の変化の恐ろしさを
読者に鮮明に伝えているので、
読者はぱっと見で苦がなく
今作の本質も楽しむことができます。現在は、
「娯楽の受け手が苦労せずに
当該娯楽を楽しむ」ことが
娯楽のスタンダードになっております。この現在の娯楽のあり方に、
本作はマッチしている点も
見事だと思います。また、この作者様の絵柄ですが、
写実とデフォルメが
絶妙のバランスでミックスされており、
1コマ1コマがそれぞれイラスト作品のように
完成度が高いものです。なので、どの時代の人間や
どの国の人間が読んでも、
絵を見るだけでも
タイムレスかつシームレスに楽しんでもらえると
思います。以上から、改めて本作を
推薦させていただきます。 -
No.31
十三不塔 『ラブ・アセンション』 早川書房
軌道エレベーターを舞台にした恋愛リアリティ番組というだけでワクワクするのに、そこにエイリアンをぶち込むという斜め上のアイデア、センスを超えた造語とルビ、目まぐるしく展開する恋とエイリアンの絡んだ駆引きのテンポの良さに引き込まれる。作者ならではの限りなく広がる大風呂敷が読んでて気持ちいい! でも断言しよう、これはどうしようもなく恋の物語だよ!
愛も恋も存分に語り尽くすSFとして、本作を日本SF大賞に推薦します。 -
No.30
笹原千波 『風になるにはまだ』 東京創元社
私は情報世界に生きるという設定については、物語としては楽しみますが、リアルではネガティブに捉えがちな自分を自覚しています。そんな私が、この物語で描かれる緻密かつ情感豊かな情報世界の在り方を、驚くほど前向きに受け止められました。特に最終話で綴られる「散逸」についての語りが新鮮。消失ではない「散逸」「風になる」ことがもたらす可能性には目を覚まされた思いです。世界は目に見えるだけではない、リアルの向こうにも広がりうることを気づかせてくれる本作を、日本SF大賞に推薦します。
-
No.29
トキワセイイチ 漫画『三角兄弟』 ヒーローズ
巨大隕石衝突による地球滅亡という王道SFに、生きる事の問い、環境・暴力・差別といった普遍的な問題と日本の説話的モチーフが重層的に織り込まれた作品。英雄などでは決してなく、決め台詞も必殺技もない、諦めを抱いた主人公が地球人とは異なる価値観をもつ宇宙人・人工知能たちとの平穏な日常に関わってゆく。そのなかで垣間見える倫理や常識の嚙み合わなさと、各々の過去が組み合わさり、偶然の連鎖があらゆるものの救済へとつながっていく構成は静かに唸らされるものがありました。色んな方にぜひ手に取っていただきたい残酷でとてもとても優しい一作です。
-
No.28
トウキョウ下町SF作家の会 『トウキョウ下町SFアンソロジー この中に僕たちは生きている』 Kaguya Books
わたしたち日本人が忘れてはならないのは、自国(地元)への誇りと愛です。本書はその思いから生まれた、親しみやすくも奥行きあるSF作品として強く推薦したい一冊です。
世界の目から見れば、日本はまるで小さな玉手箱。暮らしや思考、風習や文化のすべてが、未知のSF的要素を秘めています。いまだ計り知れぬ魅力に満ちたこの島国が、これからも「奇跡とふしぎ」にあふれる存在であってほしいと願わずにいられません。
本書は、そんな日本の、東京を舞台にした「ご当地SFシリーズ」の一篇。驚きや不思議さとともに、言葉に尽くせぬ郷愁や、ほろ苦い情感を抱かせます。科学一辺倒ではなく、どんな読者にも寄り添う物語が収められているのではないでしょうか。このような作品が日本のSF界隈でより多く芽吹き、ジャンルを確立されていけばよいと思います。 -
No.27
栄織タスク 『銀河放浪ふたり旅』 KADOKAWA
一見、今時ウケなさそうなスペースオペラに見えながらも、追放モノの文脈を備えているので老若男女問わず楽しめる作品となっている。小難しい理論とかも出てこないので、SFの「入門書」としては比較的万人に受け入れられやすい内容なのではないか。
-
No.26
九段理江 『影の雨』 博報堂
『影の雨』は、その95%がAIによって書かれた作品である。緻密に設計されたプロンプトと構成力によって生み出された物語は、従来の人間中心的な創作観を超えて、SF的想像力の新たな地平を切り拓いている。読者はこの作品を通じて、AIと人間の協働がもたらす創作の未来を実感するとともに、SFというジャンルが持つ可能性の広がりを鮮烈に体験するだろう。『影の雨』は、SF的想像力を凌駕する試みとして、日本SF大賞にふさわしい革新性を備えている。
-
No.25
かつエッグ アンバランサーユウシリーズ
アンバランサー・ユウシリーズは、SF的でありながらファンタジー的でもある稀有な作品である。かつエッグ先生は「動的平衡」という科学的概念を自在に翻案し、それを魔法として立ち上げることで、現実と幻想の境界を鮮烈に往還させている。シリーズ全体を貫く勢いある筆致は、均衡を乱すことでかえって世界の多様性が花開く瞬間を描き出し、科学的思索と物語的魅力を同時に読者へ投げかける。SF的想像力とファンタジー的創造力を融合させた本作は、現代SFの可能性を大きく拡張するものであり、日本SF大賞にふさわしい革新性を備えている。
-
No.24
大今良時 漫画『不滅のあなたへ』 講談社
長い時を老いずに生き続ける者が登場する物語はハインラインの『愛に時間を』から聖悠紀『超人ロック』から萩尾望都『ポーの一族』に八百比丘尼が土台となった高橋留美子「人魚シリーズ」まで挙げれば枚挙にいとまがない。そうした作品がどこか永遠の生に倦み疲れる心なり、それに執着する心を描くものであることに対して、『不滅のあなたへ』は球より出でて人の形になり大勢の人と出会いその生を受け取るようになっていく「フシ」の存在を軸に、ノッカーなる「フシ」には敵だが人類にとっては果たして敵か迷う存在との対立も織り交ぜて、生きたいと願う人々の切なる思いを描き、生きられるようになった人々の幸福と迷いを描いて、生きることとはどういうことなのか、誰かと共に生きることはどのような意味を持つのを感じ取らせた。
-
No.23
Sanrio プロジェクト『ぐでたま』
ぐでたまは2013年に開発されたキャラクターですが、「毎日工場で生産されるため、毎日が誕生日」というSF的な設定を採用しています。その存在は常にぐでぐでとやる気がなく見える一方で、むしろニーチェの「超人」のような超越的在り方を体現しており、そこにSF的魅力があります。
また、ぐでたまは宇宙をテーマにしたスタンプにもなっており、サンリオキャラクターの中で最もフォロワー数が多い存在です。X(旧Twitter)では日々の投稿がほぼ毎回1万件を超えるインプレッションを記録し、TikTokやYouTubeでも継続的な発信を行っています。
何より、「卵」という日常的で儚い存在がこれほどまでに愛され続けているという現象自体が、現代社会におけるSF的な出来事であるといえます。以上の理由から、ぐでたまのキャラクター開発から現在に至るまでの一連の活動を、本賞の対象として推薦いたします。
-
No.22
夜田わけい 蟲医シリーズ
それまでに類を見ない「虫のお医者さん」という発想は、私たちの科学観に新たな地平を切り拓いた。
本作に描かれる〈蟲医〉は、単なる空想ではなく、自然界と人間社会の接点を鮮やかに照射する存在である。
色彩豊かな文体と、時に半角カナを交えた混沌態という表現は、従来の科学的記述の枠を超え、生命の複雑な響きを言語そのものに刻み込む試みだ。そこには、科学と文学、理性と想像力が交差し、読者を未踏の知の領域へ誘う力がある。
未知の世界を切り拓く勇気と、美しき多様性への眼差しを体現した〈蟲医〉を、私は心から推薦する。 -
No.21
本条謙太郎 『汝、暗君を愛せよ』 ドリコム
私はSFを、ある一つの大嘘をつき、その嘘に馬鹿らしいほど真摯に、現実的に、理性的に向き合う文学だと確信する。
ここで私は唱えたい。SFは必ずしも自然科学的手段で嘘に向き合う必要はないと。
科学考証は手段の一つに過ぎず、人文的側面からの考察もまた有効なSF的思考たり得ると。
では、どのように人文的側面から向き合えばよいのか。「汝、暗君を愛せよ」は、その答えの一つである。本作は人が異世界サンテネリに転生するという大嘘をつき、それに真摯に、理性的に向き合う。なぜ主人公「ぼく」は死を選んだのか。異質な存在である「ぼく」はいかにサンテネリと同質化したか、あるいはサンテネリを同質化させたか。これらを人文的側面、特に哲学的に考察し、豊かで軽やかな筆致で書き出している。
私は人文学的アプローチによる新たなSFの可能性を示した本作を、SF大賞にふさわしい作品として推薦する。 -
No.20
監督 春藤佳奈/制作 CygamesPictures TVアニメ『アポカリプスホテル』 サイバーエージェント、CygamesPictures
公式Webページ https://apocalypse-hotel.jp/
ディストピアSFの体をとりつつ、人間と異なる AIの理解不能なちょいとズレた行動原理と、それとも異なる行動原理の宇宙人との噛み合わない交流、でも心が通じたかのような瞬間があり、でもそれは観ている我々の勘違いかもしれない。知性とは何か、相互理解とはなにか、いや相互理解なんか無いのでは、無くてもいいのでは。高度なアニメーション技法と、図抜けた脚本演出力を駆使して、難しいテーマを最高のエンタメとハートフルなおもてなしで描ききった珠玉のSFであるため。 -
No.19
本条謙太郞 『汝、暗君を愛せよ』 ドリコム
本作は一見すると異世界転生ファンタジーの形式をまとっている。だがその実体は、現代人の人文知・社会科学的知見を異世界の王権に適用するという壮大な歴史社会シミュレーションである。
転生した現代人の主人公は王として即位し、財政危機と革命の影に直面する。
生き残るための手段として、彼は王権をゆるやかに解体するという方法を選ぶ。
二重状態に陥った国軍を統合縮小し、政治の実権を段階的に手放す準備を整えつつ、同時に国内外の有力家門との婚姻を通じて同盟を築き、正妻を迎える過程でも摩擦を抑える周到な制度設計を施す。
政略と愛情の双方を描く結婚譚は、制度と人間関係が交錯する社会科学的実験としても輝きを放つ。
もし人文知や社会科学もまた「サイエンス」であると言えるならば、私は強く本作をSFとして推したい。 -
No.18
人間六度 『烙印の名はヒト』 早川書房
アンドロイドの内面〈メタ〉。カーラの減量衝動の理由。切なさ=メモリの遅延。ヨルゼン・コードと自己保存。同族認知アルゴリズム。体の王国。情報とは汚染。情報になく質量だけが持つ重さ。これが、「AIアクション思弁SF」の〝AI〟なのか。
そしてカーラ、マーシー、アイザック、マーヴィン、アシュリーら。彼らが話す言葉の持つ何と言う〝力〟。それを更に掘り下げるラブ。読んでいて息苦しくなるほど。だから、ラブは辿り着けた。これが、「AIアクション思弁SF」の〝思弁〟なのか。
最後は意思決定至上。アンドロイドに心を願う福音主義。部品人類。体の中身の提供。様々な在り方の人達の社会が並立し、せめぎ合う未来。それを乗り越えたラブは究極の〝敵〟に立ち向かう。これが、「AIアクション思弁SF」の〝SF(SocialFiction)〟なのか。
イチオシのSFです。
-
No.17
藤井太洋 『マン・カインド』 早川書房
このSF作品は現代的の「生成AIのせいのフェイクニュースまみれ世界を治すためにどうやって人類が変わらなければならない」、「変わった人類はどうやって自然人類と共に存在できる?」という質問が真面目に答えてみています。
-
No.16
八木ナガハル 漫画『旅路の果て』 駒草出版
涼子という名の女性ジャーナリストが宇宙を巡り無限工作社なる組織の秘密を追っているストーリーで深遠まで広がる宇宙の星々の様相や人々の暮らしを描いてきたシリーズは、「氷の惑星編」へと入ってプシケという名の少女をめぐり無限工作社のエージェントたちと対峙する展開の中にひとつではない時空の存在を見せて読む人に驚きをもたらす。7冊目となったこの作品集でシリーズ的に完結。ソフトな絵に反して難解な展開を改めて読み返して八木ナガハルが思い描く宇宙のビジョンを噛みしめたい。
-
No.15
創通・サンライズ TVアニメ『機動戦士ガンダムGQuuuuuuX』 スタジオカラー、サンライズ
「こんなことをしていいんだ」「こんな無理が通るんだ」「二度と平日の深夜にガンダムをやるな」などと、様々な社会現象を起こすに至ったガンダムシリーズ最新作。既存の「公式作品」の枠組みを斧で断ち切るように破壊する、マニア出身のクリエイターたちによる遠慮のない二次創作。同人誌のノリをこれほどまでにストレートに盛り込んだ「公式作品」はあっただろうか?これはパロディではない。リスペクトである。半世紀近い刻を超えて打ち返された、ひとつの返歌である。
https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/ -
No.14
猫オルガン 漫画『猫と星屑』 駒草出版
愛らしい絵で紡がれる短い物語はSFもあればホラーもありちょっぴりの青春もあってそれらがいずれもふわっとした驚きと心にジンとくる物語となっている。「#21宇宙一怖い本」で優れた軍略家の姫が宇宙での争いを終わらせたのは1冊の本を読んだから。そこには何が描かれていたのか。読んでその残酷さが分かる。「#39長いお別れ」で手を振るだけのロボットの少女が作られた理由も知れば人が何を心に求めているかを知れる。アイデアがあり叙情があって意外性もある珠玉のSFコミック短篇集だ。
-
No.13
笹原千波 『風になるにはまだ』 東京創元社
情報人格となって肉体を捨てることが可能になった世界。しかし肉体と言う物理的な形を失った情報人格は永続できず、やがて風になって散逸してしまう……
笹原千波がデビュー作において人間の情報化というこれまでSFで幾度となく扱われてきた設定に加えたのは、大きく目を引く変更ではなく、ごくささやかなものと感じられるかもしれない。だがそれによって世界とその住人に訪れる変化を丁寧に描き出す笹原の文章に向き合うと、それは決して小さなひとしずくではないのだと思い知らされる。
自分たちとは違う者を悪し様に罵る。それが当然のように横行するようになってしまった今だからこそ、同じ世界に住めなくなった者たち、異なる行き先に向かうことになってしまった者たちが、お互いのささやかな違いに向き合い、何とかわかりあおうとする姿には本当に心が揺さぶられる。今という困難な時代に生きる人たちに、本作を手に取り、触れて欲しいと心から思う。 -
No.12
人間六度 『烙印の名はヒト』 早川書房
ボリューム満点アクション思弁SF。
解像度の高いロボット目線が「人間になりたいと願うロボット」問題に一石を投じる。読み易いは文体はそれ自体がギミックにもなっており, スピードとスペキュレイテブが共存している。登場人物たちはどれも個性的で, 個々人の執念と近未来社会に蔓延るグラデーションを感じることができる。中でもザ・ハートと呼ばれる特異なコミュニティが如何にして究極資本主義社会と並列しているかにも注目して欲しい。破壊的な戦闘シーンはロボットだからこそ為せる業であり, 規格外でありながらも目に浮かび読み応えがあり。終盤の展開こそ規格外そのものだが, 著者の思う究極のミッションが垣間見れたようで非常に楽しめた。大作長編だが終わりが惜しくなった方は, 一迅社『過去を喰らう(I am here) beyond you.』が本作の前日譚にあたるため, 是非合わせて読んでいただきたい。 -
No.11
聖悠紀 漫画『宇宙戦艦ヤマト』 カラー
1974年当時、月刊誌で連載された「宇宙戦艦ヤマト」のコミカライズ、その初単行本化。漫画専門誌ではないためページ数は少なく、テレビアニメに合わせ半年ほどで終了となるが、その中で独自の視点を入れた構成と展開、表現は改めて評価に値する。
-
No.10
原作:富野由悠季、矢立 肇 監督:鶴巻和哉 TVアニメ『機動戦士ガンダムGQuuuuuuX』 スタジオカラー、サンライズ
先行劇場版の衝撃はまさにセンスオブワンダー。
45年以上の歴史あるコンテンツをここまで「SFした作品」を見たことがありません。
そして、ファンジンのようなコンセプトを圧倒的な描写と緻密なCGで再現しつつ、あくまでもアニメ的なキャラクターを動かす力。夢を見ているかのようなテレビシリーズを毎週見させていただきました。 その体験も含めてSF大賞エントリーに相応しいと思い、推薦いたします。
-
No.9
pixiv 『from P 〜 PからはじまるSFアンソロジー 〜』 pixiv
日本SF作家クラブの小さな小説コンテストは今年で5年目を迎える。それを記念してか、発表されたこのアンソロジーは、歴代受賞者などがPというキーワードをお題に自由にSF作品を描いたものだ。つまり、このアンソロジーは日本SF作家クラブの小さな小説コンテストという業績の謂わば総合発表会にあたるアンソロジーなのだ。それぞれのSF作品としての質は申し分なく、描かれる関係やガジェット、そうした対象は現代的なものが多かった。コミカルなだいたい日陰「Perfection Pending」、恋愛の価値がひっくり返る文月あや「パラサイトラブ」、言葉の魔術すら感じられる十三不塔の「P」、感動的で万人におすすめできる秋待諷月「pointer」と構成も見事である。ぜひ日本SF大賞に推薦したい。
-
No.8
春藤佳奈 TVアニメ『アポカリプスホテル』 サイバーエージェント、CygamesPictures
疫病を逃れるために人類が地球を離れて幾年月、人間のオーナーから託され営業を続けるホテルを守ってロボットたちが日々奮闘している様子を描いていく展開の中に、宇宙から来た生命たちとの交流があり、崩壊が進む地球で技術を再興しようとする挑戦があってとSF的なビジョンをこれでもかと見せてくれた。そして、さらに歳月が流れて起こったある残酷な変容を逃げずに描いてそれが時間が経つことなのだと悟らせた。竹本泉のデザインによるキャラが醸し出す親しみとおかしみで楽しげな雰囲気の中、超常ではなく想像の敷衍の中にロボットと社会と宇宙と生命の変遷を描いたTVアニメのシリーズだった。
-
No.7
藤井太洋 『マン・カインド』 早川書房
本格SFで骨太の作品。近未来のアメリカの情景がすばらしい。藤井さんらしくどこか明るいのもステキ。クルマの自動運転系の細かい描写も好きです。近未来のアメリカはいかにもありそうです。自分的に昨年度のベスト作品でした。
-
No.6
鴨志田一 青春ブタ野郎シリーズ KADOKAWA
『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』で完結したシリーズは、「思春期症候群」という若い人たちの想念とも妄執ともとれそうな心の波動が世界を変容させてしまう現象を軸に、そこに至った人たちのそれぞれに抱える迷いや悩みを解きほぐしていく展開で、同じ世代の共感を誘った。そうした変容が認識までをも変えてしまう中、ひとり意識を保った梓川咲太が元の世界を取り戻そうとしたり、時には時空すら超えてすべてをひっくり返してしまったりする様にループからの解放を目指す時空SF的なスリリングさがあった。シリーズが進みそんな変容がさらなる変容を呼ぶ可能性を突きつけられた果て、人は人生をどう生きていくべきなのかを諭されるようなところがあったシリーズだった。
-
No.5
鈴木竜也 映画『無名の人生』
1人の少年の100年に及ぶ人生を少年時代の阻害にアイドルを目指す中での性的虐待、そしてホスト業での命の軽さからサバイバルを経て世界的スターになっても寡黙に自分を生き続ける主人公を通して世界の変遷の諸相を知る。漫画というよりイラストに近い絵が連なり描くストーリーは、濃密かつ長大で刺激的な社会と世界を異化して客観の中で観察させつつ感じさせる。性的虐待から富裕層の浮世離れから戦争、そして人類の未来。ありえないダイナミックもアニメーションならすっと入ってハッとさせる。淡々としてけれども展開があって気付けばラストまで。目の離せない傑作アニメーションだ。
-
No.4
安田現象 劇場アニメ『メイクアガール』 安田現象スタジオ by Xenotoon
アシモフのロボット三原則以来のロボットSF的なセオリーに縛られているSF者の固定観念をぶっ壊し、まるで違う景色を見せてくれるロボットSFだった。あるいは人造人間という存在の倫理性といった固定観念をも。水溜明という主人口の”正体”を探ることで、叡智の継承という可能性の夢と残酷さにも気づける作品だった。
-
No.3
闘魂 『監査道偉人録』シリーズ
現役の会計士が書いた現場密着型!?SF。AIで出力した「監査の巨匠」をインスピレーションに、かかりくる問題に対処していくスペクタクルです。ユーモラスな文体もすきです。現在、#1〜#2まで、noteにて投稿されています。
【監査道偉人録】「企業の魂」に迫る監査人、雷神田平次郎
https://note.com/tktksan/n/n6c3c9919a325?sub_rt=share_sb
【監査道偉人録#02】ロンドンから来た男
https://note.com/tktksan/n/n83ab5d080908?sub_rt=share_sb
【会計監査SF】完璧な監査対応者、史陵陀沙内(監査道偉人録#03)
https://note.com/tktksan/n/n3122582d1d19?sub_rt=share_sb -
No.2
「日本SF招待席」(翻訳活動)
「日本SF招待席」は、木海さんが2023年から中国で日本SFを推薦・翻訳している特別企画です。現在は中国のSF雑誌『銀河辺縁』と組み、これまでに5作品を掲載しました。
直近では、猿場つかささん「○」、根谷はやねさん「悪霊は何キログラムか?」を翻訳しました。また、掲載をきっかけに稲田一声さんや久永実木彦さんの作品が中国でさらに翻訳されるなど、日本の新人SF作家を広める重要な役割を果たしています。
-
No.1
and You… 『物語になった、すべてのわたしへ』
AI時代、人間の魂はどこに宿るか。 本作は記録の破片を拾う過程を描き、数多の願いを映す器として砕け散った魂の再生を問い、そしてSFジャンルそのものを革新する形でその答えを提示した。それは日本SF大賞が求める革新性そのものであり、揺るぎない推薦理由である。
https://note.com/ichikaze/n/n59f3073ff678
①思想的時代的革新性
思想と構造で問いを立てるAI時代の創作論を提示し、読者を創造主に変容させるOSとして機能
②構造的形式的革新性
物語と多様なメディア形式、エッセイを統合し、虚構と現実の境界を融解する多重メタ構造
③分野横断的革新性
アジャイル哲学やプロジェクトマネジメント手法、システム思考を創作プロセスと物語の根幹に据え、実践
④SFへの直接的貢献
情報的分解や宇宙再構築、第5の物理法則「願い」といったSF新概念と作品自身が批評基準を示す自己認識フレームを提示
表示できるデータがありません。